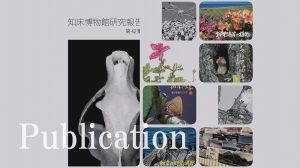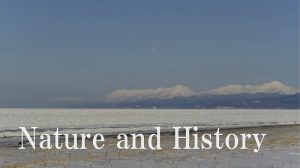特別展図録
知床博物館で毎年1回開催される特別展の図録です。ミュージアムショップでの販売のほか、知床博物館協力会で通信販売も承ります。
目次
- はじまり
- 基盤
- 繁栄
- 改革
- 変化
- 出かけよう
第41回 サケの長い旅
2021年発行、A5判変、12 pp(オールカラー)、1,200円
目次
- サケの誕生
- 海へ向かうサケの子供達
- サケの回遊
- 帰ってきたサケ!
- 産卵場所を目指して川を遡る!
- オスのケンカ
- メスの産卵床づくり
- 横からみたサケの産卵床
- サケの産卵
- 長い旅の終わり
第40回 丘に眠るオホーツク文化
2018年発行、A5判、52pp、800円
目次
- 文化のうつりかわり
- オホーツク文化のくらし
- チャシコツ岬のはたらき
- トビニタイ文化の誕生!
- コラム1:オホーツク人の古代クッキング!
- コラム2:土器はどのように作られた?
第35回 自然と歴史が結んだ絆—竹富町・弘前市と斜里町との交流の歴史
2014年発行、A4判、81 pp、600円
目次
- 竹富町と斜里町の交流のはじまり
- 竹富町と斜里町の交流のあゆみ
- コラム・定置網漁業を通じた竹富町との交流
- コラム・農業を通じた竹富町との交流
- メッセージ・40年の「絆」に乾杯よせて(那根 操)
- 竹富町の概要
- 弘前市との交流のきっかけとなった歴史
- 慰霊祭第20回記念座談会
- 弘前市と斜里町の交流の歩み
- コラム・斜里ねぷたの経緯と今
- メッセージ・友好都市30周年に寄せて(福真幸悦)
- 弘前市の概要
- 斜里に消ゆ(「東奥日報」特集記事再録)
第34回 オホーツク海岸の石
2012年発行、B6判変(95×172 mm)、48 pp(オールカラー)、500円
目次
- はじめに
- オホーツク海沿岸の地質図と観察地
- 石の種類
- オホーツク海岸の石が生まれた時代
- 海岸の石と砂はどのように運ばれてきたのでしょうか?
- 観察地
- 宗谷岬(丘陵地形)
- 稚内市東浦(アンモナイト化石)
- 猿払村鬼志別(石炭)
- 道の駅さるふつ公園(蛇紋岩と変成岩)
- 浜頓別町宇曽丹(砂金)
- 中頓別町(鍾乳洞)
- 神威岬(緑色岩)
- ウスタイベ岬(貫入岩)
- 興部川(泥岩と花崗岩)
- モベツ川(金鉱石)
- コムケ湖(潟湖)
- 湧別川(黒曜石)
- サロマ湖(泥岩)
- 常呂川(石灰岩とチャート)
- 能取岬(珪質頁岩)
- 能取岬灯台(水冷火砕岩)
- 網走市ポンモイ(柱状節理)
- 小清水原生花園(潟湖と火砕流)
- 小清水原生花園(鳴り砂)
- 斜里川(軽石と砂鉄)
- 斜里町峰浜(安山岩)
- 斜里町真鯉(メノウ)
- オシンコシン崎(柱状節理)
- 斜里町宇登呂(奇岩と水冷火砕岩)
- 斜里町岩尾別(断崖と温泉の滝)
- 知床岬(奇岩と水冷火砕岩)
- 羅臼町瀬石(海の中の温泉)
- 羅臼町天狗岩(ジャスパー)
- 植別川(緑色凝灰岩)
- 標津町薫別(海食台地)
- 野付半島トドワラ(砂嘴と沈降)
- 春別川(根釧原野と沈降)
- 花咲岬(砂岩と上昇)
- 花咲岬(車石)
- オホーツク海岸の生い立ち
- 北海道の地質区分
- 前期白亜紀(神居古潭帯・イドンナップ帯・蝦夷層群)
- 後期白亜紀(常呂帯・根室層群)
- 古第三紀〜中期新第三紀(日高累層群)
- 後期新第三紀(新旧の火山活動)
- 第四紀(海流と海岸地形)
- おわりに
第33回 発掘されたウトロ遺跡群
2011年発行、210×200 mm、32 pp(カラー10ページ)、400円
目次
- ウトロ地域の遺跡群
- 海岸付近の遺跡
- ウトロ遺跡
- ペレケチャシ遺跡
- オロンコ岩チャシ遺跡
- ウトロ西1遺跡
- チャシコツ崎周辺の遺跡群
- チャシコツ岬下A遺跡
- チャシコツ岬下B遺跡
- チャシコツ岬上遺跡
- ウトロチャシ遺跡
- 幌別1遺跡
- 段丘面上の遺跡
- 幌別河口遺跡
- ウトロ滝上遺跡
- ウトロ高原4遺跡
- ウトロ地域の地質と遺跡の成立
- ウトロ地域の地形と地質
- ウトロ地域の遺跡の立地環境と成立条件
第32回 こんなに多様な知床の鳥たち
2011年発行、210×200 mm、32 pp(カラー10ページ)、400円
目次
- 多様な環境に多様な鳥類が生息
- 営巣環境と巣-1
- 営巣環境と巣-2
- 営巣環境と巣-3
- 羽色の違い-1
- 羽色の違い-2
- くちばしと餌-1
- くちばしと餌-2
- 足の形-1
- 足の形-2
- つばさの形
- 渡り鳥と留鳥-1
- 渡り鳥と留鳥-2
- 数の多い鳥・少ない鳥-1
- 数の多い鳥・少ない鳥-2
第31回 斜里川の自然
2009年発行、211×200 mm、32 pp(カラー9ページ)、400円
目次
- 川の概要
- 地史
- 歴史
- 植物
- 魚類
- 両生・爬虫類、無脊椎動物
- 鳥類
- 哺乳類
- 川遊びの注意
第30回 知床の動物たちにひそむ危険と対処—自然を楽しむために—
2009年発行、210×200 mm、32 pp(カラー10ページ)、400円
目次
- ヒグマ
- ヒグマのいる場所を知る・1
- ヒグマのいる場所を知る・2
- ヒグマのいる場所を知る・3
- ヒグマのいる場所を知る・4
- ヒグマのいる場所を知る・5
- ヒグマのいる場所を知る・6
- ヒグマと距離を置く
- ヒグマと出会ったら
- ヒグマによる人身事故・1
- ヒグマによる人身事故・2
- ヒグマ対策の現状
- エキノコックス
- エキノコックスの生活サイクルと人への感染経路
- エキノコックスを避けるためにキツネの生態を知る
- エキノコックス症にかからないために
- エキノコックス症の感染例と現状
- ハチ
- ハチの生活史
- ハチに刺されないために
- ハチに刺されたら?
- ハチの巣を取り除くには
- ハチによる事故の状況
- マムシ
- クモ
- ダニ
- 昆虫類
- 海の動物たちにひそむ危険
第29回 知床のシダ
ポケットに入るハンディーなサイズの野外図鑑です。見出し68種に知床半島産80種のリスト。2007年発行、B6判変(95×172 mm)、64 pp(オールカラー)、400円
第28回 来運1遺跡
2006年発行、210×200 mm、21 pp(オールカラー)、400円
縄文中期の焼けた土葺伏屋式建物跡が大量の炭化材として発掘された来運1遺跡の紹介、および斜里町内の縄文時代の遺跡の概観。
目次
- 北海道斜里町来運1遺跡とは
- 2004年の発掘のようす(出土遺構と遺物から)
- 2005年の発掘のようす(焼けた土葺伏屋式建物跡の全体像)
- 斜里町内出土の縄文各期の住居跡とその特徴
- 縄文早期
- 縄文晩期
- 縄文中期
- 縄文後・晩期
- 来運1遺跡出土の土葺伏屋式建物跡の構造
- 縄文期に構築された住居・建物跡
- 来運1遺跡・土葺伏屋式建物発見の意義(道内・東北・北陸地方などとの比較)
データブック知床・2010
2010年発行、A5判、149 pp(カラー4ページ)、500円
前巻の「データブック知床・2005」以降に追加となった情報を盛り込み、大幅に内容を更新。
目次
- 地形
- 山岳
- 河川
- 湖沼
- 滝
- 地質
- 岩石
- 鉱物
- 火山灰と火砕流
- 温泉
- 新第三紀層名の比較
- 気象
- ウトロの平年値
- 羅臼の平年値
- 日降水量
- 最大1時間降水量
- 月降水量の多い方から
- 月降水量の少ない方から
- 年降水量の多い方から
- 年降水量の少ない方から
- 最高気温
- 最低気温
- 最大風速と風向
- 最大瞬間風速と風向
- 月間日照時間の多い方から
- 月間日照時間の少ない方から
- 年間日照時間の多い方から
- 年間日照時間の少ない方から
- 積雪差日合計
- 積雪差月合計
- 積雪差寒候期合計
- 月最深積雪
- 流氷
- 生物
- 生物種数
* 植物種数
- * 動物種数
- * 希少種
- * 希少藻類
- * 希少植物
- * 希少陸産貝類
- * 希少昆虫
- * 希少魚類
- * 希少両棲類
- * 希少爬虫類
- * 希少鳥類
- * 哺乳類
- * 外来種
- * 外来植物
- * 外来昆虫
- * 外来魚
- * 外来鳥類
- * 外来哺乳類
- * 歴史
- * 遺跡
- * 知床世界遺産地域の歴史年表
- * 保護地域
- *自然保護地域
* 付表・生物リスト
- 変形菌
- 藻類
- 海藻類
- 淡水藻類
- 植物
- コケ植物
- シダ植物
- 種子植物
- 菌類
- 陸産貝類
- 昆虫類
- 蜻蛉目
- 革翅目
- 直翅目
- 半翅目
- 広翅目
- 脈翅目
- 鞘翅目(甲虫目)
- 膜翅目
- 双翅目
- 鱗翅目
- 脊椎動物
- 軟骨魚類
- 硬骨魚類
- 両棲類
- 爬虫類
- 鳥類
- 哺乳類
- 文献
第27回 データブック知床・2005
2005年発行、A5判、119 pp(絶版)
目次
- 地形
- 知床の山岳
- 知床の河川
- 知床の湖沼
- 知床の滝
- 地質
- 知床の岩石
- 知床の鉱物
- 知床の火砕流・火山灰
- 知床の温泉
- 新第三紀層名の比較
- 気象
- ウトロの平年値
- 羅臼の平年値
- 最高気温
- 最低気温
- 最大風速・風向
- 日降水量
- 最大1時間降水量
- 月間降水量の多い方から
- 月間降水量の少ない方から
- 月間日照時間の多い方から
- 月間日照時間の少ない方から
- 最深積雪
- 知床の流氷
- 生物
- 知床の植物種数
- 知床の動物種数
- 知床の希少藻類
- 知床の希少植物
- 知床の希少陸産貝類
- 知床の希少昆虫
- 知床の希少魚類
- 知床の希少爬虫類
- 知床の希少鳥類
- 知床の希少哺乳類
- 知床の外来植物
- 知床の外来昆虫
- 知床の外来魚類
- 知床の外来鳥類
- 知床の外来哺乳類
- 歴史
- 知床の遺跡
- 知床世界遺産地域の歴史年表
- 付表・生物リスト
- 藻類
- 菌類
- 植物
- シダ植物
- 裸子植物
- 被子植物
- 陸産貝類
- 昆虫類
- 蜻蛉目
- 直翅目
- 半翅目
- 甲虫目
- 膜翅目・アリ
- 膜翅目・ハチ
- 鱗翅目・チョウ
- 鱗翅目・ガ
- 脊椎動物
- 軟骨魚類
- 硬骨魚類
- 両生類
- 爬虫類
- 鳥類
- 哺乳類
- 文献
第26回 活火山羅臼岳
2004年発行、211×200 mm、32 pp、400円。
多くの登山者にも愛されている羅臼岳。その火山活動の姿と歴史を紹介。
目次
- 北海道の活火山
- 知床半島の形成
- プレート運動
- 海底火山活動と陸上火山活動
- 羅臼岳の地形と登山道
- 海底火山活動
- ゴジラ岩とマッカウス洞窟
- 幌別の台地と断崖
- 木下小屋〜弥三吉水
- 羅臼岳(陸上火山活動)
- 弥三吉水〜極楽平
- 銀冷水〜大沢
- 羅臼平〜岩清水
- 頂上部の溶岩円頂丘
- 連山頂上部の断層地形
- 断層地形と高山植物
- 頂上からの風景
- 屏風岩と平坦面
- 泊場
- データが示す羅臼岳の最近の活動
- 2300年前の活動
- 1500年前の活動
- 700年前の活動
- 火砕流・溶岩図
- 硫黄の沈殿
- 湧き水
- 天頂山
- 噴火地形
- 羅臼湖
- 予想される羅臼岳火山活動
- 山体崩壊した知床硫黄山
- セントヘレンズ山の山体崩壊
- 羅臼岳噴火モデル
- 羅臼岳形成史
- 200万年前
- 12万年前
- 10万年〜数万年前
- 2300年前
- 1900年前
- 1500年前
- 700年前
- 予想される噴火
第25回 骨の図鑑
2003年発行、210×200 mm、36 pp(カラー10ページ)、400円
目次
- エゾシカ全身骨格
- 頭の骨(頭蓋骨・下顎骨)エゾシカ
- 頭の骨(頭蓋骨・下顎骨)エゾシカ以外の動物
- 背骨(頸椎)エゾシカ
- 背骨(頸椎)ゴマフアザラシ・ミンククジラ・イシイルカ・ヒグマ
- 背骨(胸椎)、肋骨 エゾシカ
- 背骨(胸椎)、肋骨 ゴマフアザラシ・イシイルカ・ヒグマ
- 背骨(腰椎)エゾシカ
- 背骨(腰椎)ゴマフアザラシ・イシイルカ・ヒグマ・キタキツネ
- 背骨(仙骨尾椎)、寛骨 エゾシカ
- 背骨(仙骨尾椎)、寛骨 エゾリス・ゴマフアザラシ・ヒグマ・キタキツネ・イシイルカ・ネズミイルカ
- 前肢の骨 エゾシカ
- 前肢の骨 ヒグマ・キタキツネ・エゾリス・エゾユキウサギ・エゾモモンガ・トド・ゴマフアザラシ
- エゾモモンガ全身骨格
- エゾユキウサギ全身骨格
- ゴマフアザラシ全身骨格
- エゾリス全身骨格
- キタキツネ全身骨格
- ヒグマ全身骨格
第24回 知床の樹木
2002年発行、B6判変(95×172 mm)、48 pp(オールカラー)、400円
ポケットに入るハンディーなサイズ、葉っぱで調べる樹木の野外図鑑です。
第23回 知床の漁業
2001年発行、210×200 mm、36 pp(カラー10ページ)、400円
目次
- 知床漁業のすべて
- 知床漁業の特色
- サケ・マス定置網漁
- 刺網漁
- イカ釣りとサンマ棒受網漁
- ウニ漁とエビ漁
- タコ漁とかご漁
- 地引き網と船引き網
- ホタテガイけた網漁
- 漁業協同組合
- 知床漁業史
- アイヌ文化と斜里場所
- 斜里の近代漁業史
- 資料一覧
- 羅臼の漁業
- 海難事故
第22回 斜里町の縄文時代—衣食住とお墓—
2001年発行、210×201 mm、32 pp、400円
目次
- 縄文時代の暮らし
- 衣類
- 食べ物
- 住まい
- 縄文時代のお墓
- 時期別分布
- 時期別形態および特徴
- ストーンサークルと環状土籬
- 斜里町内で発掘された主な縄文遺跡
- 縄文早期遺跡
- 縄文前期遺跡
- 縄文中期遺跡
- 縄文後期遺跡
- 縄文晩期遺跡
- 斜里町内全域の遺跡分布図
第21回 宇宙から見た知床ポスター
1999年発行、菊全版、2 pp、400円
- 地球観測衛星ランドサットから見た北海道
- 気象衛星ノア撮影のオホーツク海の流氷
第20回 知床の海獣狩猟
1998年発行、211×200 mm、36 pp(カラー10ページ)、400円
目次
- 氷海の海獣狩猟
- 北方民族と海獣
- エスキモーの海獣狩猟
- 北洋の海獣狩猟
- 先史文化のなかの海獣狩猟
- 知床の先史文化と海獣
- オホーツク文化と海獣狩猟
- アイヌの海獣狩猟
- アイヌ文化と海獣
- 斜里でのアザラシ漁
- 近代の海獣狩猟
- 開拓使とラッコ猟
- 戦争と海獣
- 斜里での海獣利用
- 大型捕鯨
- 戦後の海獣狩猟
- アザラシ漁
- 小型沿岸捕鯨
- イルカ猟
- 展示資料一覧
- 知床の海獣
- 斜里海岸のストランディング・レコード
第19回 知床の温泉
1997年発行、210×200 mm、33 pp(カラー2ページ)、400円
目次
- 温泉とは
- 知床半島の温泉
- 知床硫黄山新噴火口
- カムイワッカの滝
- 宇登呂温泉
- 岩尾別温泉
- ウナベツ温泉
- 越川温泉
- 清里温泉
- 斜里温泉
- 羅臼温泉
- 相泊・瀬石温泉
- 薫別温泉
- 川北温泉
- 温泉と火山・断層
- 泉質と地質環境
- 温泉を探そう
- 温泉の効能
- 温泉のマナー
- 温泉分析値
第18回 鹿 DEER
1996年発行、34 pp(カラー4ページ)、400円
目次
- シカのからだ
- 総論
- シカという動物
- 世界のシカの仲間
- 日本のシカ
- シカってどんな動物?
- 蹄(ひづめ)をもつ
- 反芻(はんすう)する
- 上顎の前歯(切歯)がない
- 角
- 各論: 知床のシカ・エゾシカ
- エゾシカの一年
- 受精から誕生
- 出産
- ほ乳期
- 初めての越冬
- こどもからおとなへ
- 老化そして死
- エゾシカと人間
- 古代人とシカ
- 乱獲と再分布
- シカは増えているのか
- シカをめぐる問題
- シカと人間の未来
第17回 知床の蝶と蛾
1995年発行、210×119 mm、32 pp(カラー4ページ)、400円
目次
- チョウとガの生態
- 形態
- 卵
- 幼虫
- 蛹
- 成虫
- 生態
- 系統上での分類
- 生活
- 生息環境
- 知床のチョウとガ
- 知床のチョウ
- 知床のガ
- チョウとガをもっと楽しく知るために
- チョウとガのおもしろさ
- 人とのかかわり
- 採集方法
- 標本の作り方
- 私とチョウ(進 基)
- 私とガ(川原 進)
第16回 北海道と知床の化石
1994年発行、210×200 mm、34 pp、400円
目次
- 化石は何を教えてくれるか
- 生物進化
- 北海道の地質構造と化石
- クビナガリュウ
- アンモナイト
- デスモスチルス
- カイギュウ
- タカハシホタテガイ
- ナウマンゾウとマンモスゾウ
- 北海道の動物のルーツを探る
- 化石が語る北海道の生い立ち
- 道東の地質構造と化石
- 石灰岩(北見)
- アンモナイトとイノセラムス(根室・釧路・佐呂間)
- 淡水産植物化石(北見)
- ベヘモトプス(足寄)とデスモスチルス(北見)
- ペンギン(網走)
- タカハシホタテガイ(阿寒)
- 網走構造線と火山活動・珪藻化石
- シロウリガイ(斜里)
- クジラとイルカ(斜里)
- マンモスゾウ(羅臼・別海)
- セイウチと石炭(斜里)
- 化石が語る道東と知床の生い立ち
- 化石の復元
第15回 峰浜のむかし
1994年発行、210×200 mm、32 pp、400円
目次
- シュマトカリベツ9遺跡発掘調査
- 斜里平野周辺の遺跡分布
- 地形変化と遺跡
- 最終氷期
- 後氷期(縄文文化の始まり)
- 縄文海進最盛期
- 砂丘の形成
- 古斜里湖の形成
- 古環境
- 地下の情報収集
- 古環境変化の解析
- 年代を知る
- 海水面の変化を知る
- 植生や気温・気候変化を知る
- トーツル沼試料による古環境変化の解析
- 峰浜地区の遺跡分布
- 河川沿いに分布する遺跡
- 海岸や砂丘上に分布する遺跡
- 台地上に分布する遺跡
- 峰浜地区時期別遺跡分布
- 峰浜の遺跡と自然環境とのかかわり
- 縄文早〜前期
- 縄文中〜晩期
- 続縄文〜擦文文化期
第14回 斜里町の教育100年
1993年発行、211×200 mm、36 pp、400円
目次
- 語り継ぐ教育
- 初期の学制
- 学校史
- 斜里小学校
- 朱円小・中学校
- 以久科小・中学校
- 川上小・中学校
- 峰浜小・中学校
- 三井小・中学校
- 越川小・中学校
- 大栄小学校
- 宇登呂小・中学校
- 富士小・中学校
- 岩尾別小・中学校
- 来運小学校
- 日の出小学校
- 豊里小学校
- 真鯉小・中学校
- 朝日小学校
- 斜里中学校
- 斜里高等学校
- 大谷幼稚園
- 小・中学校系統図
- 戦争と子供たち
第13回 近世の斜里
1992年発行、210×200 mm、36 pp、400円
目次
- 北海道の近世
- 蝦夷地と幕府・松前藩
- 近世の斜里
- 古文献に登場する斜里
- アイヌ文化期の遺跡から見た斜里
- 津軽藩士の殉難
- シャリ場所
- 商場と場所請負制
- シャリ場所分設
- シャリ場所を請負った人たち
- シャリ場所の産物
- シャリ場所のようす
- 斜里アイヌの人口
- 斜里町年表(近世)
第12回 宝石と鉱石が語る北海道・知床の生いたち
1990年発行、210×200 mm、34 pp(カラー3ページ)、400円
目次
- 宝石と地球の運動
- ダイヤモンド—マントルからの宝石—
- ヒスイ—高圧の変成作用で生まれた宝石—
- 北海道のヒスイ産地 神居古潭
- コランダム・ガーネットの日高山脈
- 水晶の仲間—火山マグマの熱水で生まれた宝石—
- 黒曜石—自然界のガラス—
- 鉱石と地球の運動
- 黒鉱(くろこう)鉱床
- 海嶺熱水性鉱床
- キースラーガー(別子形含銅硫化鉄鉱)
- キースラーガーと下山鉱山
- 鉱脈鉱床
- 北海道の金鉱床—鴻之舞鉱山
- 知床の鉱脈鉱床—新ウトロ鉱山
- 火山性鉱床 硫黄
- 活発な活動を続ける知床硫黄山
- 堆積鉱床
- 褐鉄鉱
- 砂鉄
- 砂金と砂白金
- マンガン
- 宝石と鉱石が語る北海道・知床の生い立ち
第11回 流氷
1990年発行、212×200 mm、32 pp、400円
- 世界最南端の流氷接岸地斜里
- 流氷の形成とオホーツク海の特殊地形
- オホーツク海の二層構造
- 海氷の形成
- 流氷の衛生写真
- 1987年〜1988年の流氷の動き
- 流氷の接岸前後の気象変化
- 流氷とシバレ
- 海明け前後の気象
- 流氷があたえてくれた知床の地形と自然
- 冬と子供達
- 流氷と海鳥類
- 流氷とオオワシ
- 流氷とアザラシ
- 流氷と漁業
- 流氷と農業
- 流氷と塩害
- 流氷と観光
- 流氷と歴史=過去の気候変化と文化の盛衰=
- 地球温暖化のために流氷が来なくなる?
- 幻氷と流氷に関するデータ
- 冬の風景
第10回 斜里町産業発達史
1988年発行、215×201 mm、36 pp、400円
知床博物館開館10周年記念・町民憲章制定20周年記念
目次
- 斜里町産業史の概要
- 漁業の歴史
- 農業の歴史
- 林業の歴史
- 主な出来事
第9回 消えた北方民族—オホーツク文化の終えん—
1987年発行、208×200 mm、36 pp、400円
目次
- 三つの文化
- ピラガ丘遺跡群
- 古代ピラガ丘村の発掘
- ピラガ丘遺跡群から発見された遺物
- オホーツク文化
- 土器の変化
- 住まいの様子
- 衣服のいろいろ
- 交通の方法
- 道具のいろいろ
- シャーマンの世界
- 天上の国へ
- オホーツク物語
第8回 斜里平野のおいたち
1986年発行、211×201 mm、28 pp、400円
目次
- 斜里平野の地質
- 知床半島と斜里平野
- 斜里平野の基盤
- 斜里平野周辺の地形
- 地形発達史
- 屈斜路スコリア流の堆積
- 屈斜路スコリア流堆積後の侵食
- 屈斜路軽石流堆積物Iの流下
- 段丘面・山麓扇状地面・新期扇状地面の形成
- 縄文海進
- ラグーンの形成
- 現在
- 火山灰
- 降下火山灰と火砕流
- 火山灰の地層断面
- 火山灰分布
- 火山灰のなかみ
- 砂丘
- オホーツク海の海岸線と貫入岩
- 砂丘の形成
- 鳴り砂
- オホーツク海沿岸の砂丘砂分析
- 古気象と古環境
- 調査方法
- 代表的な花粉化石
- 花粉分析—気温の変化—
- 代表的なケイ藻化石
- ケイ藻分析—海から陸への変化—
- 氷河時代の斜里
- 周氷河現象
- インボリューションと凍結割れ目
- 遺跡と砂丘形成
- 斜里平野地形図
第7回 知床の鳥
1985年発行、216×200 mm、24 pp、400円
目次
- 海の鳥
- 水辺の鳥
- 草原の鳥
- 森林の鳥
- 高山の鳥
- 流氷の海の鳥
- 知床の鳥の季節変化
- 先人の見た知床の鳥
第6回 よみがえる古代文化
1984年発行、210×201 mm、32 pp、400円
目次
- 尾河遺跡
- 古代の尾河村
- 姿をあらわした村
- 家のかたち
- 祭のあと
- 死者を送る
- 最後の縄文土器
- 続縄文土器
- 土器の形と文様
- 突く・刺す
- 切る(1)・穴をあける
- 切る(2)・削る・掘る
- たたく・こする
- 飾る
- 交易
- 残された動物の骨
- 続縄文文化と弥生文化
- 文化財保護のお願い
第5回 知床に輝く星たち
1983年発行、211×201 mm、20 pp(絶版)
目次
- 1981年部分日食
- 日食観測の歴史
- 月
- 1982年皆既月食
- 春の星座
- 夏の星座
- 秋の星座
- 冬の星座
- すい星
- おりひめ星とひこぼし星のおはなし
- 星・仲間
- 天体ドーム
第4回 知床のヒグマ
1982年発行、215×200 mm、25 pp(絶版)
目次
- 世界のクマ
- ヒグマの分布
- ヒグマの歯と年齢
- ヒグマは何を食べているか
- ヒグマの繁殖
- ヒグマの冬ごもり
- ヒグマの四季
- ヒグマの行動
- ヒグマと人間
第3回 斜里—下町の歴史散歩—
1981年発行、221×200 mm、40 pp、400円
目次
- 下町の歴史散歩
- 古文献による斜里
- 斜里場所
- 津軽藩士の北方警備
- 明治時代の下町
- 大正時代の下町
- 昭和初期の下町
- 古老座談会による大正時代の下町
第2回 オクシベツ川流域の先史文化
1980年発行、220×200 mm、36 pp(カラー3ページ)、400円
目次
- オクシベツ川流域の遺跡群
- 環状土籬と環状列石
- オクシベツ川流域の自然環境
- 斜里町の遺跡分布と時代区分
- 道具のいろいろ
- 発掘調査から報告書の作成まで
- 関連科学の応用
- 文化財保護のお願い
第1回 吉積長春遺作展
1979年発行、239×226 mm、28 pp(カラー12ページ)、400円
知床をこよなく愛した郷土の日本画家、吉積長春の作品を紹介。