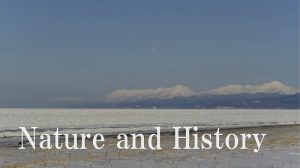イベント一覧(2024年)
お問合わせは知床博物館まで(tel 0152-23-1256)
12月
知床博物館 第43回特別展「大標本展」
知床国立公園60周年・世界遺産20周年を記念して、「大標本展」を開催しています。開館から約 50年間の間に集められた標本から約1000点を蔵出ししました。斜里町内で捕獲され北海道最後の記録となった絶滅動物ニホンカワウソの毛皮や、斜里町内の多くの電柱が改良されるきっかけとなった ウトロで感電死したシマフクロウ、斜里町内で最後の殺傷事件を起こしたヒグマの剥製など、いずれも物語のある標本ばかりです。今しか見られない標本も多数展示しています。ぜひお立ち寄りください。
- 会期:〜2月28日(金)
- 場所:交流記念館ロビー
講座「ワンランクアップのトンボ玉作り」
これまで博物館講座では、基礎的なトンボ玉作り講座を数回行ってきました。今回は数種類のガラスを混ぜて作る縞模様のトンボ玉や、動物など立体的なトンボ玉のストラップ作りに挑戦します。初 心者の方もご参加ください。
- 日 時:12月7日(土) 1回目:9:30〜 11:00、2回目:11:00〜12:30
- 場 所:農業資料等収蔵施設(旧朱円小学校)
- 定員:各時間4名(要申込み・小学生以上)
- 参加費:600円 (材料費)
- 講師:合地信生学芸員、戸田実琴
- 申込先:知床博物館(0152)23–1256
収蔵資料展示「冬の外套 トンビコート」
大正から昭和初期にかけて、お洒落な男性に人気だったトンビコートを展示します。袖ぐりがベスト風で大きく、着物の袖も楽に通すことが出来るため、当時の着物生活にも適していたようです。 和洋折衷の大正ロマンをぜひ感じてください。
- 会期:12月10日(火)〜12月26日(木)
- 場所:本館受付前
開館記念イベント もちつき大会
博物館が開館したのは昭和53(1978)年12月28日、今年で46周年になります。開館を記念し、恒例の臼と杵による「もちつき大会」を開催します。今年の締めと来年への期待を込め、日本の伝統行事であるもちつきに参加しませんか?あんこやきなこ、みたらしなど、いろんなお味で、つきたての柔らかいおもちを味覚でも楽しめます。暖かい服装で、ぜひご参加ください!
- 日 時:12月22日(日)10:00〜11:30(悪天候の場合は中止)
- 場所:博物館前庭
- 参加費:無料 (要申込、協力会会員優先受付)
- 定員:60名
- 申込先:知床博物館(0152)23–1256
- 協力:知床博物館協力会
11月
知床博物館 第43回特別展「大標本展」
知床国立公園60周年・世界遺産20周年を記念して、「大標本展」を開催しています。約50年来蓄積し、収蔵庫に眠っていた約1000点の生物標本を一気に蔵出ししました。 動物の剥製や骨格標本、植物の押し葉標本、魚の透明標本、昆虫標本など、知床に暮らす生き物の多様な姿を、収蔵されるまでの過程と一緒にご覧ください。知床ならではの海と陸のつながりや、生き物とのいい距離感が見えてくるかもしれません。
- 会期:〜2月28日(金)
- 場所:交流記念館ロビー
講座 特別展ギャラリートーク&バックヤードツアー「庫(くら)へようこそ」
ギャラリートークでは、大標本展の見どころを学芸員がじっくり解説します。その後は、「収蔵庫」に潜入してみませんか?普段展示されている資料は、実は博物館の所蔵品の中ではごく一部。大標本 展で展示中の生物資料と同じく、一点一点に人々の思いと貴重な情報が込められた資料たちが出番を 待っています。まるで隠し部屋のような、博物館の「裏の顔」をお楽しみに。
- 日時:11月24日(日) 10:00〜11:30
- 場所:交流記念館ロビーほか
- 定員:15名(要申込)
- 参加費:無料
- 講師:臼井 平学芸員、三枝 大悟学芸員
- 申込先:斜里町立知床博物館 (0152)23-1256
博物館講座「お気に入りの石を磨いてみよう」
山で採集した思い出の石や、人から貰ったお気に入りの石を研磨機で磨きます。1辺が5cm程度の石を準備してください。2時間でオリジナルの岩石作品をつくります。 石を切断しておきたい等のご相談は14日(木)に受け付けますので、石を持参してご来館ください。
- 日時:11月16日(土)9:30〜11:30、13:00〜15:00
- 場所:交流記念館2階 実習室
- 定員:各5名(要申込、小学生以上)
- 参加費:300円(小中学生、協力会員は無料)
- 持ち物:磨くための石、汚れても良い服装
- 講師:合地 信生学芸員
- 申込:斜里町立知床博物館 (0152)23-1256
- 相談は14日(木)9:00〜17:00(12:00〜13:00を除く)に受け付けます。
収蔵資料展示「団塊世代のトランジスタラジオ」
トランジスタラジオは、1960年代後半、若者向けラジオの深夜放送がスタートし、深夜の受験勉強 のお供として団塊の世代に受け入れられ、普及しました。小型でどこでも持ち運びができ、重宝さ れたトランジスタラジオを展示します。
- 会期:11月13日(水)〜12月8日(日)
- 場所:本館受付前
10月
知床博物館 第43回特別展「大標本展」
知床博物館は前身の「知床資料館」時代も含めると開館してから50年を超える歴史があり、収集してきた生物標本は1万点をゆうに超えています。これらの膨大な標本は野外で採集され、博物館へと収蔵されるに至るまでに1点1点歩んできたストーリーがあります。調査研究で採集されたもの、車に轢かれたもの、駆除されたもの、感電死したもの... etc。こうした物語を紐解いていくと、斜里町の豊かな自然や人間生活との軋轢など様々な特色が見えてきます。多様な生物標本の展示を通じて新たな「知床」を見つけるきっかけになれば幸いです。
- 会期:〜2月28日(金)
- 場所:交流記念館ロビー
ミュージアムカフェ 「斜里の地名の変遷」
斜里のアイヌ語由来の地名や入殖後の地名、変わった地名、知っているようで知らない地名を紹介 します。「鶴ノ巣」「鷲の巣」って?「 豊里 」の由来は ?「 朱円 」の最初の読みは?などなど。お茶しながら歴史の移りかわりを楽しみます。
- 日時:10月11日(金) 18:30〜20:00
- 場所:交流記念館応接室
- 定員:先着15名(要申込)
- 参加費:200円(協力会員無料)
- 申込先:斜里町立知床博物館 (0152)23-1256
施設公開「農業資料等収蔵施設一般公開」
「桜園のんびりバザール」にあわせて行ってきた一般公開、今年度は今回が最終回です。催し物や出店者等はSNSで告知します。
- 日 時:10月23日(水)10:00〜16:00
- 場所:農業資料等収蔵施設(旧朱円小学校)
高山植物園「草取りボランティア」
色とりどりの草花に季節を感じる草取り、今年度最終回です。
- 日 時: 10/11(金)9:00 〜10:00※雨天中止
- 場所:博物館高山植物園(ワシ小屋付近)
- 持ち物:帽子、軍手、虫除け
- 申込:不要
収蔵資料展示「おしゃれの源 羊毛ばさみ」
羊の毛刈りに使われたはさみを展示します。人々の生活やおしゃれを支えてきた羊毛の暖かさに思 いを馳せてみてください。
- 会期:10月17日(木)〜11月10日(日)
- 場所:本館受付前
博物館講座「紫金山・アトラス彗星と 土星・月の観察会」
紫金山・アトラス彗星は肉眼でも長い尾が見られると期待されており、10月12日頃から日没後の西の空に見えると予測されています。当日は土星と月も大型天体望遠鏡で観察します。
- 日時:10月18日(金)18:00 〜19:30 ※悪天候の場合は、19日(土)、20 日(日)に変更。
- 場所:博物館 前庭
- 定員:20名(要申込)
- 参加料:無料
- 講師:合地信生学芸員
- その他:小学生以下は保護者同伴。
- 申込先:斜里町立知床博物館 (0152)23-1256
9月
知床博物館 第43回特別展「大標本展」
知床博物館は前身の「知床資料館」時代も含めると開館してから50年を超える歴史があり、収集してきた生物標本は1万点をゆうに超えています。これらの膨大な標本は野外で採集され、博物館へと収蔵されるに至るまでに1点1点歩んできたストーリーがあります。調査研究で採集されたもの、車に轢かれたもの、駆除されたもの、感電死したもの... etc。こうした物語を紐解いていくと、斜里町の豊かな自然や人間生活との軋轢など様々な特色が見えてきます。多様な生物標本の展示を通じて新たな「知床」を見つけるきっかけになれば幸いです。
- 会期:9月28日(土)〜2月28日(金)
- 場所:交流記念館ロビー
知床博物館 第43回特別展講座「ギャラリートーク」
特別展開催に合わせて、担当学芸員が、展示の見どころを解説します。
- 日時:9月29日(日)10:00〜10:40
- 場所:交流記念館ロビー
- 講師:臼井学芸員
- 申込:不要
施設公開「農業資料等収蔵施設一般公開」
10月まで月1回開催の「桜園のんびりバザール」にあわせて、農業資料等収蔵施設も一般公開します。催し物や出店者等はSNSでご案内します。
- 日 時:9月25日(水)〜9月29日(日)10:00〜16:00
- 場所:農業資料等収蔵施設(旧朱円小学校)
高山植物園「草取りボランティア」
色とりどりの草花に季節を感じながら、一緒に作業してみませんか?
- 日 時: 9/13、10/11(いずれも金曜日)9:00 〜10:00※雨天中止
- 場所:博物館高山植物園(ワシ小屋付近)
- 持ち物:帽子、軍手、虫除け
- 申込:不要
「弦楽四重奏の夕べ」旧役場庁舎活用事業 サロンコンサート
今年2回目となる、旧役場庁舎を活用した室内楽コンサートを開催します。今回は2階ホールを使った弦楽四重奏で、クラシックからポピュラーまで幅広い演奏を楽しめます。
- 日時:9月27日(金)18:00開場(18:30開演)
- 場所:旧役場庁舎(旧図書館)
- 料金:無料
「蓄音器演奏会」旧役場庁舎活用事業
明治期に発売された蓄音器による演奏会を開催します。114 年前に発売されたニッポノホンという蓄音器の修復を行いました。100 年前の斜里の人々に衝撃を与え、脚光を浴びていた蓄音器の音色を楽しめる機会です。お聞き逃しなく。
- 日時:9月13日(金)18:00開場
- 場所:旧役場庁舎(旧図書館)
- 料金:無料
8月
施設公開「農業資料等収蔵施設一般公開」
10月まで月1回開催の「桜園のんびりバザール」にあわせて、農業資料等収蔵施設も一般公開します。催し物や出店者等はSNSでご案内します。
- 日 時:8月24日(土)10:00〜16:00
- 場所:農業資料等収蔵施設(旧朱円小学校)
高山植物園「草取りボランティア」
色とりどりの草花に季節を感じながら、一緒に作業してみませんか?
- 日 時:8/9、 9/13、10/11(いずれも金曜日)9:00 〜10:00※雨天中止
- 場所:博物館高山植物園(ワシ小屋付近)
- 持ち物:帽子、軍手、虫除け
- 申込:不要
収蔵資料展示「あかしのぶこデザイン協力会会員証原画展vol.2」
毎年会員に発行している、町内在住絵本作家のあかしのぶこさんによる魅力あふれるデザインの会 員証の原画展第2弾です。作品を全て入れ替えてお届けします。知床に暮らす生き物たちが活き活きと描かれていますので、ぜひご覧ください。
- 日時:8月14日(水)~9月16日(月)
- 場所:本館受付前
博物館講座 親子参加歓迎! ペルセウス座流星群と夏の星座観察会
11日から13日はペルセウス座流星群の極大日ですので、流れ星が発生しやすくなります。ほかにも 夏の星座や天の川、天体望遠鏡で土星の輪を観察します。夏の一夜、是非親子で宇宙を感じてください。
- 日時:8月12日(月) 19:30〜20:30※悪天候の場合は、13日(火)に変更。
- 場所:博物館 前庭
- 定員:20名(要申込)
- 参加料:無料
- 講師:合地信生学芸員
- その他:小学生以下は要保護者同伴。大人だけの参加も可。
- 申込先:斜里町立知床博物館 (0152)23-1256
ロビー展「はた織り作品展」
明治時代に実際に使用され、博物館に寄贈されたはた織り機が交流記念館ロビーに置かれています。 このはた織り機は、はたおりの会のみなさんに使われ、いまでも現役で作品を産み出しています。伝 統的な技術で、ひとつひとつ丁寧 に時間をかけて織られており、昔ながらの温かみのある作品だけではなく、目新しいデザインの作品も並びます。力作をぜひご覧ください。
- 会期:〜8月31日(土)まで(現在展示中)
- 場所:博物館交流記念館ロビー
7月
講座「知床火山活動観察会」
カムイワッカ川の温泉、知床五湖、知床峠を回り、知床の火山活動を感じてみましょう。
- 日時:7月6日(土) 8:30〜15:30・小雨決行
- 集合場所:知床博物館
- 講師:合地 信生学芸員
- 定員:6名(要申込/先着/ 中学生以上)
- 持ち物:昼食、濡れてもよい服、雨具、軍手、タオル、飲み物など
- 参加費:1,000円 (保険料、専用靴貸出込み)※協力会員半額
- 申込先:斜里町立知床博物館(0152)23-1256
施設公開「農業資料等収蔵施設一般公開」
10月まで月1回開催の「桜園のんびりバザール」にあわせて、農業資料等収蔵施設も一般公開します。催し物や出店者等はSNSでご案内します。
- 日 時:7月31日(水)10:00〜16:00
- 場所:農業資料等収蔵施設(旧朱円小学校)
高山植物園「草取りボランティア」
色とりどりの草花に季節を感じながら、一緒に作業してみませんか?
- 日 時:7/12、8/9、 9/13、10/11(いずれも金曜日)9:00 〜10:00※雨天中止
- 場所:博物館高山植物園(ワシ小屋付近)
- 持ち物:帽子、軍手、虫除け
- 申込:不要
収蔵資料展示「あかしのぶこデザイン協力会会員証原画展vol.1」
毎年会員に発行している、町内在住絵本作家のあかしのぶこさんによる魅力あふれるデザインの会 員証の原画を展示します。
- 日時:7月17日(水)~8月11日(日)
- 場所:本館受付前
ロビー展「所蔵ねぷたポスター展」
昭和58(1983)年の第1回運行以来、全てのねぷたのポスターが大集結しました。紙面を飾る懐かし い催し物の写真などにもご注目ください。
- 会期:6月8日(土)〜 7月21日(日)
- 場所:交流記念館ロビー
企画展「真部 裕 昆虫コレクション展」
令和4(2022)年に故真部裕氏のご遺族から寄贈を受けた約6,000点の昆虫コレクションを展示します。ドイツ箱に収められた昆虫コレクションは宝石箱のよう。好評につき会期を延長しました。ぜひご覧ください。
- 会期:5月25日(土)〜 7月31日(水)
- 場所:博物館本館2F映像展示室
6月
講座「藻琴山地質観察会」
ハイランド小清水725から屈斜路カルデラ、藻琴山溶岩を観察しながら藻琴山の生立ちを探ります。
- 日時:6月30日(日) 8:30〜15:30 ・小雨決行
- 集合場所:知床博物館
- 講師:合地 信生学芸員
- 定員:15名(要申込/先着/小学生以上)
- 持ち物:昼食、雨具、登山靴・服、飲み物など
- 参加費:300円(保険料込み。協力会員、中学生以下無料)※協力会員半額
- 申込先:斜里町立知床博物館 (0152)23-1256
施設公開「農業資料等収蔵施設一般公開」
10月まで月1回開催の「桜園のんびりバザール」にあわせて、農業資料等収蔵施設も一般公開します。催し物や出店者等はSNSで告知します。
- 日 時:6月29日(土)10:00〜16:00
- 場所:農業資料等収蔵施設(旧朱円小学校)
「ピアノカルテットのひととき」旧役場庁舎活用事業 サロンコンサート
【室内楽コンサートのお誘い】
旧役場庁舎(旧図書館)で室内楽コンサートが行われます。元来は教会や宮廷の一室などで行われた室内楽演奏会は、シンプルだからこそ感じられる楽器ごとの個性が楽しめる編成となっています。
今回は、前半にクラシック、後半はジャズやポップスなど馴染みの曲を演奏予定です。築95年となる木造建築物で行われる室内楽の調べをお楽しみください。
- 日時:6月15日(土)15:30〜
- 場所:旧役場庁舎(旧図書館)
- 料金:無料
ロビー展「所蔵ねぷたポスター展」
しれとこ斜里ねぷたの今年の開催に向けて、知床博物館が所蔵する歴代ポスターを一挙公開します。
- 会期:6月8日(土)〜 7月21日(日)
- 場所:交流記念館ロビー
講座「遺跡巡りバスツアー」
ウトロのチャシコツ岬上遺跡(国指定)やペレケチャシ跡遺跡、羅臼ビジターセンターや標津町ポー川のカリカリウス遺跡(国指定)等を巡ります。
- 日時:6月9日(日)9:00 〜17:00頃・雨天実施
- 集合場所:知床博物館
- 講師:勝田 一気学芸員・村田 良介学芸員
- 定員:30名(要申込/先着)
- 持ち物:保険料200円、入園料330円、昼食、軍手
- 注 意:チャシコツでは急坂を上り、ポー川では木道を約1km歩きます。
- ウトロのみ参加はチャシコツ岬下に 9:50 集合です。
- 申込先:斜里町立知床博物館 (0152)23-1256
収蔵資料展示「昭和の番傘」
雨の季節です。町内の漁業協同組合や商店の名前が入ったレトロな番傘を展示します。
- 会期:6月12日(水)〜 7月15日(月•祝)
- 会場:博物館本館受付前
高山植物園「草取りボランティア」
色とりどりの草花に季節を感じながら、一緒に作業してみませんか?
- 日 時:6/14、7/12、8/9、 9/13、10/11(いずれも金曜日)9:00 〜10:00※雨天中止
- 場所:博物館高山植物園(ワシ小屋付近)
- 持ち物:帽子、軍手、虫除け
- 申込:不要
博物館みどりの日「花壇に花を植えにきませんか?」
博物館駐車場脇の花壇に、たくさんの花を植えてお客様をおもてなしする恒例行事。ぜひご参加ください。
- 日時:6月23日(日) 10:00〜12:00
- 場所:博物館前庭
- 持ち物:帽子、軍手、虫除け
- 申 込:不要
5月
企画展「真部 裕 昆虫コレクション展」
令和4(2022)年に故真部裕氏のご遺族から寄贈を受けた約6,000点の昆虫コレクションを展示します。ドイツ箱に収められた昆虫コレクションは宝石箱のよう。ぜひご覧ください。
- 会期:5月25日(土)〜 7月31日(水)
- 場所:博物館本館2F映像展示室
施設公開 農業資料等収蔵施設「春の一般公開」
農業資料等収蔵施設(旧朱円小学校)では、「春の一般公開」を行います。主に明治の開拓期から昭和にかけての産業や生活に使われていた資料を見ることができます。 また、今年もレコードなどを聴きながらゆっくりできる空間の提供と、 手作りパンやお菓子、飲み物の販売を行う「のんびりバザール」が開催されるほか、楽しいワークショップなども予定していますので、この機会にぜひご来館ください。バザールのメンバーによる「ガリ版を使った版画印刷体験」も行われます。
- 期間:5月1日(水)〜5日(日)
- 時間:9:30〜16:30
- 場所:農業資料等収蔵施設(旧朱円小学校)
版画印刷体験:4 日(土)、5日(日)、10:00~
道立北方民族博物館移動展 文化財写真ー北方民族の文化多様性を伝える&ギャラリートーク
北方地域で幅広い時代に使われた様々な文化財の高精細画像を展示する写真展です。写真と北方民 族研究のそれぞれの専門家をお招きし、見どころをじっくりと語っていただきます。
- 会期:5月19日(日)まで
- ギャラリートーク : 5月11日(土) 10 : 00 〜11:30
- 講師:城野誠治(東京文化財研究所専門員)・笹倉いる美(北方民族博物館学芸主幹)
- 場所:交流記念館ロビー
- 移動展のみの観覧・ギャラリートークともに無料です
収蔵資料展示 「昭和のレトロなマッチ箱」
昭和の頃、いろいろなお店で配られていたマッチ箱は、小さな世界に当時の風景や世相が詰め込ま れています。そんな斜里町のマッチ箱を展示します。
- 会期:5月8日(水)〜 6月9日(日)
- 場所:博物館本館受付前
4月
道立北方民族博物館移動展 文化財写真ー北方民族の文化多様性を伝える
文化財の特徴を余すことなく記録し、その魅力を輝かせる「文化財写真」。北方民族博物館と東京文化財研究所の共同研究により撮影された、北方地域に伝わる様々なモノの高精細写真を展示します。※北方民族博物館ロビー展を再構成したものです。
- 会期:4月20日(土)〜5月19日(日)
- 場所:交流記念館ロビー
- ロビー展のみの観覧は無料です
収蔵資料展示 「端午の節句の五月人形」
端午の節句は、子どもたちの邪気を払い無病息災を祈る行事です。 今回は、愛らしい端午の節句に飾る馬乗り大将と金太郎を展示します。
- 会期:4月3日(水)〜 5月5日(日)
- 場所:博物館本館受付前
- この展示の観覧料は無料です
講座「トンボ玉つくり」
ガラス棒をバーナーで溶かし、細い鉄棒に巻き付けてトンボ玉を作ります。今回は失敗しながらもたくさんの作品にチャレンジする入門コースです。色とりどりなオリジナル作品を作ってみましょう。
- 日時:4月20日(土) 9時、10時、11時、13時、14時から各1時間
- 場所:交流記念館実習室
- 定員:各時間2名(小学生以上)
- 申込み:必要(先着順)
- 申込先:知床博物館 (0152)23-1256
- 参加費:300円(協力会員、中学生以下は無料)
- 講師:合地 信生学芸員
3月
ロビー展 道東地区博物館巡回展「カメラは見た!動物たちの素顔」
道東各地の博物館学芸員や地域住民が撮影した野生動物のイチオシ写真展です。普段見なれた動物たちを「ちょっと変わった角度」からとらえました。一瞬の気を抜いた時の表情や撮影した地域ならではの動物たちの風景など、いつもと違った動物たちの素顔をお楽しみください。※本内容は美幌博物館特別展の内容を巡回展として再構成したものとなっています。
- 会期:2月27日(火)〜3月31日(日)
- 場所:交流記念館ロビー
- ロビー展のみの観覧は無料です。
収蔵資料展示 「電話番号標示板「61」」
町内のある建物で掲示されていた、電話番号標示板を展示します。斜里に電話がはじめて通じた1920(大正9)年には、町内81か所で電話が使われ、それぞれに固有の番号がありました。この「61」の電話番号標示板は、1968(昭和43)年まで変わらず使われ続けました。どこで使れていたかは、博物館でぜひお確かめください。
- 会期:3月6日(水)〜 3月31日(日)
- 場所:博物館本館受付前
- この展示の観覧料は無料です。
講座「春と冬の天体写真撮影会」
天体写真をくっきりと撮るために、星の動きに合わせて動く赤道儀を使った撮影会を開催します。 星の光はとても微量なので開放(バルブ)を使えるデジタルカメラを使って、約30秒から1分かけてじっくりと撮影し、実際にプリントしてみます。カメラは博物館で用意しますが、開放を使えるカメラがあればお持ちください。赤道儀を使って、季節の星座やオリオン大星雲の詳細な姿をカメラで捉えてみましょう。
- 日時:3月29日(金)20:00〜21:30※悪天候の場合は、30日(土)か31日(日)に変更
- 場所:博物館前庭
- 定員:10名
- 申込み:必要(先着順)
- 申込先:知床博物館 (0152)23-1256
- 参加費:無料
- 持ち物:防寒具(あればカメラ)
- 講師:合地 信生 学芸員
講座「スノーシューで歩く森の観察会」
知床博物館周辺の森では、様々な野鳥や砂丘ならではの木々を観察できます。また、雪の上には動物たちの痕跡が残り、竪穴住居跡やアイヌ時代のチャシ跡などの遺跡もあります。夏には歩きにくい森も、雪の上ならスノーシューで快適に歩けます。身近だけど見どころ沢山、春の森を散策してみましょう。
- 日時:3月30日(土)9:00〜12:00
- 場所:博物館周辺(博物館集合)
- 定員:15名(小学3年生以下は保護者同伴)
- 申込み:必要(先着順)
- 申込先:知床博物館 (0152)23-1256
- 参加費:保険料200円(協力会員は無料)
- 持ち物:寒くない服装、おやつ、温かい飲み物(スノーシューは博物館で用意します)
- 講師:臼井 平・村田 良介 学芸員
2月
ロビー展 姉妹町盟約50周年記念「竹富町との交流のあゆみ写真展」
竹富町との姉妹町盟約の調印は昭和48 年 (1973)1月10日。その後は農業や漁業の交流、物産展の開催、児童・生徒や町民号による相互訪問などが続いています。これら半世紀にわたる交流を写真で振り返ります。
- 会期:2月1日(木)〜22日木)
- 場所:交流記念館 ロビー
- ロビー展のみの観覧は無料です。
ミュージアムカフェ 姉妹町盟約50周年記念 「カフェ種子取(たなどぅい)祭」
竹富島の種子取祭は五穀豊穣を願う伝統的な農耕儀礼で、毎年旧暦の9月から10月頃に9日間にわたって行われ、7日目と8日目には芸能が奉納されます。国の重要無形民俗文化財。お茶しながら、赤瓦民家や展示資料に囲まれて姉妹町の祭りや生活のお話を聞きます。
- 日時:2月22日(木)18:30〜20:00
- 場所:交流記念館 展示室赤瓦民家前
- 参加費:大人200円(協力会員は無料)
- 定員:先着20名(要申込み)
- 講師:飯田泰彦 町史編集係長(竹富町教育委員会町社会文課)他
- 申込先:知床博物館 (0152)23-1256
収蔵資料展示 「御殿飾りの雛人形」
3月3日の桃の節句に合わせ、段飾りとはちょっと違う、建物付きの雛人形を展示します。宮殿のような建物にお内裏様とお雛様が並ぶ「御殿飾り」は 、江戸時代に生まれ 、西日本を中心に昭和30年代まで流行しました。斜里町富士で飾られた雅な雛人形をご覧ください。
- 会期:2月7日(水)〜 3月3日(日)
- 場所:博物館本館受付前
- この展示の観覧料は無料です。
ロビー展 道東地区博物館巡回展「カメラは見た!動物たちの素顔」
普段見なれた動物たちを「ちょっと変わった角度」からとらえた写真展です。一瞬の気を抜いた時の表情や撮影した地域ならではの動物たちの風景など、いつもと違った動物たちの素顔をお楽しみください。※本内容は美幌博物館特別展の内容を巡回展として再構成したものとなっています。
- 会期:2月27日(火)〜3月31日(日)
- 場所:交流記念館ロビー
- ロビー展のみの観覧は無料です。
1月
ロビー展「地図・ちず・マップの世界」
知床博物館で所有している地図を紹介します。見れば見るほど「沼」にはまる地図の世界。学校で使った地図、ロシア語の地図、5 万分の1地形図から斜里市街図、古地図などを展示します。
- 会期:1月10日(水)~28日(日)
- 場所:交流記念館 ロビー
- ロビー展のみの観覧は無料です。
ミュージアムカフェ「地図カフェ」
ロビー展で展示する地図をはじめ、講師が最近気になる地図事情について、お茶しながら気軽にトークします。
- 日時:1月27日 ( 土 )18:30〜20:00
- 場所:交流記念館 2階応接室
- 参加費:大人 200 円 ( 協力会員無料 )
- 定員:先着14 名(要申込み)
- 講師:村田 良介 学芸員
- 申込先:知床博物館 (0152)23-1256
収蔵資料展示 冬の防寒着 角巻
寒さが厳しい冬の間、明治から昭和にかけて使われた角巻は、嫁入り道具としても扱われた高級品でした。昭和15(1940)年ごろ、富士在住の女性が斜里のまちで購入した角巻から、当時の冬のおしゃれを感じてください。
- 会期:1月4日(木)〜 2月4日(日)
- 場所:博物館本館受付前
- この展示の観覧料は無料です。
講座「冬の星座観察会」
冬の星座には恒星で一番明るいシリウスなど明るく輝く一等星が7つもあり、有名なオリオン座も冬の夜空を飾っています。また、星の誕生を教えてくれるすばるやオリオン座大星雲を天体望遠鏡で観察します。
- 日時:1月12日(金) 19:00〜20:00(悪天候の場合は13日(土)か14日(日)に変更)
- 場所:博物館前庭と天体ドーム室
- 申込み:必要
- 申込先:知床博物館 (0152)23-1256
- 参加費:無料
- 服装:防寒具
- 講師:合地 信生 学芸員
講座 親子参歓迎!「お絵かき巣箱作り」
自然豊かな斜里町では市街地でも様々な野鳥が子育てをしていま す。野鳥の「巣作りから子育て」を観察するための巣箱を一緒に作ってみませんか。できあがった巣箱にはお絵かきをして博物館の裏庭に仕掛けます。参加者は、来年から巣箱を開けて中の様子を観察できます。モモンガやリスも入るかも!
- 日時:1月20日(土)9:00 〜12:00
- 場所:交流記念館実習室
- 対象:小・中学生(小学3年生以下は要保護者同伴)
- 参加費:無料
- 定員:15組
- 持ち物:暖かい服装、軍手
- 講師:臼井 平 学芸員
- 申込み:必要
- 申込先:知床博物館 (0152)23-1256
12月
ミュージアムカフェ「カフェ斜里平野」
特別展「斜里平野の魅力」の会期終了が迫っています。展示や図録では触れていないことや斜里平野の魅力をスライドや地図を見ながら語り合います。お茶しながら、あらためて魅力を再発見しましょう!
- 日時:12月15日(金) 18:30〜20:00
- 場所:交流記念館 2F 応接室
- 講師:村田良介学芸員
- 参加費:大人 200 円(協力会員無料)
- 定員:先着14 名(要申込み)
- 申込先:知床博物館 (0152)23-1256
- 18:00 〜18:30 にギャラリートーク (展示解説)を行います(無料)。特別展は12月17日(日)まで。
講座「北海道の石でキーホルダー作り」
北海道には黒曜石の産地白滝、羅臼と留辺蘂にはジャスパー、旭川神居古潭にはヒスイなど魅力的な石が産出します。研磨機を使ってオリジナルのキーホルダーを作ってみましょう。
- 日時:12 月16 日(土)10:00 〜12:00
- 場所:交流記念館実習室
- 参加費:400円(中学生以下と協力会員は無料)
- 定員:10 名(要申込み)
- 申込先:知床博物館 (0152)23-1256
- 服装等:汚れても良い服装、 事前に爪を切っておいて下さい。
収蔵資料展示 「生活と共に歩んできた鉄瓶」
湯を沸かし、茶碗に注ぐ道具として生活に欠かせない鉄瓶。当時の囲炉裏があった様子など想像しながらご覧下さい。
- 会期:12月6日(水)〜 12月27日(水)
- 場所:博物館本館受付前
- この展示の観覧料は無料です。
開館記念イベント「もちつき大会」
博物館が開館したのは昭和53 (1978)年12月28日、今年で45周年になります。開館を記念し、恒例の臼と杵による「もちつき大会」を開催します。今年の締めと来年への期待を込め、日本の伝統行事であるもちつきに参加しませんか?あんこやきな粉、みたらしなど、いろんなバリエーションで、 つきたての柔らかいおもちを味覚でも楽しんでください。
- 日時:12月24日(日) 10:00〜11:30(悪天候の場合は中止)
- 場所:博物館前庭
- 申込み:必要・定員60 名 (協力会会員 優先受付 )
- 申込先:知床博物館 (0152)23-1256
- 参加費:無料
- 服装:暖かい服装
- 協力:知床博物館協力会
11月
特別展 斜里平野の魅力〜人と自然による景観形成の歴史〜
四季折々の雄大な風景をわたしたちに魅せてくれる斜里平野がいかにして今日の景観へと変わっていったのか?そこには大きな気候変動と開拓者のたゆまぬ努力の歴史がありました。この特別展をご覧になることで 、きっと平野の魅力と歴 史を学ぶことができます。開催期間中にぜひご来館ください。
- 会期:9月23日(土)〜12月17日(日)
- 場所:交流記念館ホール
- ※ロビー展のみの観覧は無料です。
特別展講演会「アイヌ語地名から探る斜里平野・1万年の歴史」
特別展「斜里平野の魅力」に伴う特別講演会を開催します。
講演会:「アイヌ語地名から探る斜里平野 1万年の歴史」
この講演では、斜里に残る「シュマトゥカリ」という不思議なアイヌ語地名を手がかりとして、アイヌの人たち、そして人類はいつから斜里平野に住んでいたのか?という大きな問題にふれていきます。
マンモスを追ってきた旧石器人、気候の温暖化に適応して土器を発明した縄文人、オホーツク海からやってきたオホーツク文化人、さまざまな人類が混じり合い、変容し、交流した斜里平野は、日本列島のなかで、実はもっとも興味深い歴史を秘めた場所なのです!自然と人間がつくってきた1万年以上前の氷河期からたどる斜里平野の「景観(ランドスケープ)」の歴史をのぞいてみましょう。
- 日時:11月25日(土) 開演 13:30 〜15:00 頃
- 場所:博物館本館2階 映像展示室
- 料金:無 料(※要事前申込み/定員30名)
- 講 師:小野 有五さん 北海道大学名誉教授、1948年東京都生まれ。専門は地理学(理学博士)。「たたかう地理学」(2013年)で日本地理学会賞、日本人文地理学会賞を受賞。
- その他:講演会終了後に特別展のミニレクチャーを行います (希望者)。
- 申込先:知床博物館 (0152-23-1256)
収蔵資料展示 「根北線の定期券」
越川と斜里の間を結んだ国鉄根北線は、1970(昭和45)年に廃線になるまで、地域の大切な交通手段でした。学生たちが毎日のように使った小さな定期券から、当時の賑わいに思いを馳せてみてください。
- 会期:11月8日(水)〜 12月3日(日)
- 場所:博物館本館受付前
- ※この展示の観覧料は無料です。
博物館講座「秋の星座と木星・土星観察会」
秋の星座には、明るく輝く一等星はありませんがアンドロメダ大星雲やペルセウス座の二重星団など天体望遠鏡で見て楽しい天体が多くあります。また、木星と土星もまだ見頃です。ぜひご参加ください。
- 日時:11月10日(金)19:00〜20:00
- 集合場所:知床博物館交流記念館前
- 講師:合地 信生学芸員
- 参加費:無料
- 申込み:必要(定員6名)
- 申込先:知床博物館(0152)23ー1256
- 持ち物:暖かい服装
10月
第42回特別展 斜里平野の魅力〜人と自然による景観形成の歴史〜
斜里平野の人と自然の営みに注目した特別展を開催しています。明治時代の殖民区画をベースにして景観が作られてきた歴史を探ります。
- 会期:9月23日(土)〜12月17日(日)
- 場所:交流記念館ホール
- ※ロビー展のみの観覧は無料です。
高山植物園「草取りボランティア」
今年最後の草取りボランティアです。是非ご参加ください。
- 日時:10月13日(金) 9:00〜10:00(雨天中止)
- 場所:高山植物園(博物館裏のワシ小屋付近)
- 持ち物:帽子、軍手、虫除け
- 申し込み:不要(当日、直接現地にお越しください)
施設公開「農業資料等収蔵施設一般公開」
農業資料等収蔵施設(旧朱円小学校校舎 )を一般公開します。ワークショップも行います。あわせて、音楽などを聴きなが らゆっくりできる空間の提供と、手作りパンやお菓子、飲み物の販売を行う「のんびりバザール」も開催されますので、この機会にぜひご来館ください。
- 日時:10月25日(水) 9:30〜16:30
- 場所:斜里町農業資料等収蔵施設(旧朱円小学校)
- ※郷土史などの朗読会等も予定しています。
博物館講座「網走・常呂の地質観察会」
網走地域には知床半島より少し古い約1,000万年前の海底火山活動の地層が分布し、常呂地域にはさらに古い約6,000万年前の地層があります。これらから道東のでき方について考えてみます。
《おもな観察ポイント》
浜小清水海岸の鳴り砂、ポンモイの柱状節理、二ツ岩の水冷破砕岩、 能取岬の海食台地、常呂川で黒曜石探し、常呂変成帯の石灰岩
- 日時:10月21日(土)8:30〜16:30
- 集合・解散場所:知床博物館交流記念館前
- 講師:合地 信生学芸員
- 参加費:300円(協力会会員は無料)
- 定員:6名
- 申込み:必要
- 申込先:知床博物館(0152)23ー1256
- 持ち物:弁当、雨具、筆記道具
姉妹町盟約50周年記念「赤瓦三線ミニライブfrom竹富島」
姉妹町盟約50周年と交流記念館30周年を記念して、芸能の宝庫である竹富島で活躍している方々による三線ミニライブを開催します。竹富町の伝統的建物である赤瓦民家のもと、臨場感と島の情緒たっぷりに演奏します。南国の風を是非堪 能してください。
- 日 時:10 月 29 日(日)開 演:13:30
- 場所:交流記念館交流展示室
- 共催:知床博物館、姉妹町友好都市交流を進める会、竹富島三線ライブ実行委員会
- 料金:無料
- 申込:不要
収蔵資料展示 「澱粉工場の法被(はっぴ)」
町内では、かつて延べ200軒を超える澱粉工場が営まれていました。以久科で昭和40年代まで営まれていた山田澱粉工場の法被から、活気あふれる生産現場の雰囲気を想像してみてください。
- 会期:10月4日(水)〜 11月5日(日)
- 場所:博物館本館受付前
- ※この展示の観覧料は無料です。
9月
第42回特別展 斜里平野の魅力〜人と自然による景観形成の歴史〜
斜里平野の人と自然の営みに注目した特別展を開催します。明治時代の殖民区画をベースにして景観が作られてきた歴史を探ります。
- 会期:9月23日(土)〜12月17日(日)
- 場所:交流記念館ホール
- ※ロビー展のみの観覧は無料です。
ギャラリートーク 第42回特別展 斜里平野の魅力〜人と自然による景観の歴史〜
- 日時:①9月24日(日)10:00〜10:40 ②9月30日(土)11:00〜11:40(二回とも同じ内容です)
- 場所:交流記念館ホール
- 講師:村田 良介学芸員
- 申込:不要
- 講座「斜里平野の魅力地訪問」の同日セット参加がおススメです。
講座「斜里平野の魅力地訪問」第42回特別展 斜里平野の魅力〜人と自然による景観形成の歴史〜
- 日時:①9月24日(日)13:00〜16:00 ②9月30日(土)13:00〜16:00(別の場所に行きます)
- 集合場所:交流記念館ホール
- 講師:村田 良介学芸員
- 定員:各12名
- 申込:必要・先着順
- 申込先:知床博物館(0152)23-1256
- ギャラリートークの同日セット参加がおススメです。
高山植物園「草取りボランティア」
色とりどりの草花に季節を感じながら作業をしてみませんか?ご都合のつく時に是非ご参加ください。
- 日時:9月8日(金)9:00〜10:00(雨天中止)
- 場所:高山植物園(博物館裏のワシ小屋付近)
- 持ち物:帽子、軍手、虫除け
- 申し込み:不要(当日、直接現地にお越しください)
施設公開「農業資料等収蔵施設一般公開(秋期)」
農業資料等収蔵施設(旧朱円小学校)の秋の一般公開を行います。春の「音響機器」展示を引き続き開催し、蓄音機の実演奏や来館者がお持ちになるレコード鑑賞会なども行います。 音楽を聴きながらゆっくりできる空間の提供と、 手作りパンやお菓子、飲み物の販売を行う「のんびりバザール」も開催されますので、この機会にぜひご来館ください。
- 会期:9月20日(水) 〜24日(日)
- 時間:9:30〜16:30
- 場所:農業資料等収蔵施設(旧朱円小学校)
- 23日、24日の13:00頃に、蓄音機を使ったSPレコードの視聴を行います。
博物館講座「中秋の名月と土星・木星観察会」
大型天体望遠鏡でお月見をしましょう。隕石が衝突した月のクレーターや溶岩が流れた月の海を観察します。また、土星の環や木星の縞模様も見ます。盛りだくさんのメニューですので是非ご参加ください。
- 日時:9月29日(金)19:30〜20:30※悪天候の場合は30日(日)に延期
- 集合場所:知床博物館交流記念館前
- 講師:合地 信生学芸員
- 参加費:無料
- 申込み:必要
- 申込先:知床博物館(0152)23ー1256
収蔵資料展示 「アナログ時代の秤(はかり)」
これ、どっちが重い?郵便で送るならいくら? ちょっとした時に何かと必要な秤。デジタルが主流になった昨今では珍しく感じられるかもしれない、 アナログ式の秤を展示します
- 会期:9月6日(水)〜 10月1日(日)
- 場所:博物館本館受付前
- ※この展示の観覧料は無料です。
8月
ロビー展「はた織り作品展」
はたおりの会のみなさんが、ひとつひとつ丁寧に時間をかけて織った作品を展示します。新作も出品しますのでお楽しみに。
- 会期:8月5日(土)〜9月9日(土)
- 場所:交流記念館ホール
- ※ロビー展のみの観覧は無料です。
移動展示「音響機器展」
5月に朱円の農業資料等収蔵施設で開催された「音響機器展」を旧役場庁舎「葦の芸術原野祭」で一部移設します。
- 会期:8月4日(土)〜8月19日(土) 10:00〜17:00(月・火は休館)
- 場所:斜里町旧役場庁舎 ※本移動展は「葦の芸術原野祭」に併せ開催
- 入場料:無料
高山植物園「草取りボランティア」
色とりどりの草花に季節を感じながら作業をしてみませんか?ご都合のつく時に是非ご参加ください。今回は第2金曜日が祝日のため、8月10日(木)になりました。
- 日時:8月10日(木)9:00〜10:00(雨天中止)
- 場所:高山植物園(博物館裏のワシ小屋付近)
- 持ち物:帽子、軍手、虫除け
- 申し込み:不要(当日、直接現地にお越しください)
施設公開「農業資料等収蔵施設一般公開」
6月から旧朱円小学校で、月に1 回のペースで町民団体主催の「桜園のんびりバザール」が開催されています。これにあわせて、農業資料等収蔵施設も毎月一般公開します。9月は5日間連続での公開です。
- 会期:8月30日(水) 、9月20日(水)〜24日(日)
- 場所:農業資料等収蔵施設(旧朱円小学校)
博物館講座「夏の星座観察会」
こと座のベガ、白鳥座のデネブ、 ワシ座のアルタイルを結ぶ夏の大三 角形や天の川にある星雲・星団を天 体望遠鏡で観察します。
- 日時:8月5日(土)20:00〜21:00※悪天候の場合は8月6日(日)に延期
- 集合場所:知床博物館交流記念館前
- 講師:合地 信生学芸員
- 参加費:無料
- 申込み:必要
- 申込先:知床博物館(0152)23ー1256
収蔵資料展示 「樺太の白樺製カゴ」
私たちの住んでいる斜里町でも、 身近に見られる白樺とフレップ(苔桃)。樺太に住む少数民族の二ブフの人々がフレップを入れて運ぶために使った、白樺製のカゴを展示します。
- 会期:8月9日(水)〜 9月3日(日)
- 場所:博物館本館受付前
- ※この展示の観覧料は無料です。
7月
ロビー展 「ホネざんまい」
東京農業大学オホーツクキャンパス の学生が博物館実習の授業で製作した、骨の標本を展示します。 オオカミウオやトドの頭骨、エゾフクロウの全身骨格や羽毛などの力作のほ か、美味しいフライドチキンでつくった骨格標本の変わり種まで、ホネざんまいでお届けします。 普段は見ることのない様々な動物の骨から、その暮らしぶりを想像することも楽しいですが、あわせて近くの大学で行われている活動を身近に感じていただけたら幸いです。
- 会期:6月29日(木)〜7月16日(日)
- 場所:交流記念館ホール
- ※ロビー展のみの観覧は無料です。
収蔵資料展示 「昭和の虫かご」
蝶、クワガタ、キリギリスや バッタなど、昆虫採集というと子供の頃が思いだされます。昭和の竹ひごや金網と板で作られた虫かごを展示します。
- 会期:7月5日(水)〜8月6日(日)
- 場所:博物館本館受付前
- ※この展示のみの観覧は無料です。
高山植物園「草取りボランティア」
色とりどりの草花に季節を感じながら作業をしてみませんか?ご都合のつく時に是非ご参加ください。
- 日時:7月14日(金)9:00〜10:00(雨天中止)
- 場所:高山植物園(博物館裏のワシ小屋付近)
- 持ち物:帽子、軍手、虫除け
- 申し込み:不要(当日、直接現地にお越しください)
博物館講座「アンモナイト石鹸作り」
アンモナイトの型にグリセリンなどの薬品を注入し、アンモナイトの形の手作り石鹸を作ります。 お風呂場のメンバーに、アンモナイト石鹸をどうぞ。
- 日時:7月30日(日) 10:00〜11:30
- 場所:交流記念館実習室
- 定員:10名(要申し込み/小学4年生以上)
- 参加費:300円(小中学生、協力会員は無料)
- 講師:合地学芸員
- 申込先:斜里町立知床博物館 (0152)23-1256
6月
ロビー展 「ホネざんまい」
東京農業大学オホーツクキャンパスの学生が博物館実習の授業で製作した、骨の標本を展示します。 オオカミウオやトドの頭骨、エゾフクロウの全身骨格や羽毛などの力作のほか、美味しいフライドチキンでつくった骨格標本の変わり種まで、ホネざんまいでお届けします。 普段は見ることのない様々な動物の骨から、その暮らしぶりを想像することも楽しいですが、あわせて近くの大学で行われている活動を身近に感じていただけたら幸いです。
- 会期:6月29日(木)〜7月16日(日)
- 場所:交流記念館ホール
- ※ロビー展のみの観覧は無料です。
講座「知床の温泉観察会」
知床半島にはいろいろな泉質の温泉が湧出しています。岩尾別温泉や瀬石温泉(羅臼町)などを訪れ、温度計とペーハー計を使って、温泉の特徴を調べます。また、周りの地質との関係から泉質を推察します。羅臼の熊の湯に入浴予定。
- 日時:6月24日(土)9:00 〜16:00(小雨決行)
- 集合場所:博物館
- 講師:合地学芸員
- 定員:6名(高校生以上)※要申し込み
- 参加費:300円(協力会員無料)
- 持ち物:雨具、昼食、入浴用タオル、長靴、筆記用具
- 申込先:知床博物館(0152-23-1256)
講座「バスで行く・・チャシコツ岬上遺跡など町内遺跡巡り」
斜里町内には約400 か所の登録された遺跡がありますが、特に著名なオホーツク文化期のチャシコツ岬上遺跡(国指定)、縄文時代の朱円周堤墓群 (道指定)、同じく来運1遺跡(町指定) をバスで巡ります。
- 日 時 :6月18日 (日) 9:00 〜15:30※雨天実施
- 集合場所:博物館
- 訪問先:チャシコツ岬上遺跡、 朱円周堤墓群、来運1遺跡など (車中での解説あり)
- 講師:村田学芸員
- 定員:30 名 (要申し込み / 先着)
- 持ち物:保険代100円、昼食(自然センター)、軍手(チャシコツ岬上遺跡は急斜面を登ります)
- その他:自然センターで映像を見ます ( 希望者 600 円 )。
- チャシコツ岬上遺跡だけの参加者は 遺跡下に10時集合。チャシコツ岬上遺跡にはウルシが繁茂しているエリアがあります。
収蔵資料展示「お菓子をいれたガラス瓶」
昭和の頃、町内の商店街など、まち角のお店で使われた、昔懐かしいガラス瓶をご紹介します。彩り豊かな駄菓子が詰められていた様子を思い出して みてください。
- 会期:6月7日(水)〜7月2日(日)
- 場所:博物館本館受付前
- ※この展示の観覧料は無料です。
博物館みどりの日「花壇に花を植えにきませんか?」
知床博物館みどりの日では毎年、博物館駐車場脇の花壇に、たくさんの花を植え、来館者を迎えてきました。 今年度も下記の通り実施します。ご都合のよろしい方はぜひご参加ください。
- 日時:6月25日(日)10:00〜12:00
- 場所:知床博物館前庭
- 持ち物:帽子、軍手、虫除け
- 申し込み:不要(当日、直接現地にお越しください)
高山植物園「草取りボランティア」
今年もまた博物館裏にある高山植物 園の草取りボランティア活動が始まりますが、今年は日程を変更します。6月から10月まで 、毎月第2金曜 ( 祝日の場合は前日木曜 ) の9時から実施します。色とりどりの草花に季節を感じながら作業をしてみませんか?ご都合のつく時に是非ご参加ください。
- 日時:6月9日(金)9:00〜10:00(雨天中止)
- 場所:高山植物園(博物館裏のワシ小屋付近)
- 持ち物:帽子、軍手、虫除け
- 申し込み:不要(当日、直接現地にお越しください)
5月
ロビー展 北方民族博物館移動展
「暖かい」だけじゃない!毛皮と北方民族の多彩な関係
&ギャラリートーク
開催中のロビー展の関連イベントとして、北海道のアイヌやグリーンランドのイヌイットなど、寒い地域の先住民族の暮らしに詳しい専門家をお招きして、毛皮をめぐる物語と展示の魅力をじっくり語っていただくギャラリートークを開催します。
お申込みは不要です。たくさんの方のご参加をお待ちしております。
- 日時:5月6日(土)10:30〜12:00
- 場所:交流記念館応接室(集合)・交流記念館ホール
- 講師:日下 稜(北海道大学低温科学研究所)
□□□是澤 櫻子(国立アイヌ民族博物館)
□□□中田 篤(北方民族博物館) - 参加費:無料
施設公開
農業資料等収蔵施設の一般公開(春期)と「音響機器展」
農業資料等収蔵施設 ( 旧朱円小学校校舎 ) の春の一般公開を行います。昨年までの展示に加え、博物館から移転 し整理中の収蔵庫も公開し、普段は見られない資料を見ることできます。また、研修スペース(旧音楽室)では、「音響機器展」を開催し、音楽などを聴きながらゆっくりできる空間の提供や、出張ミュージアムショップもオープンしますので、この機会にぜひご来館ください。
- 会期:5月6日 (土)〜5月14日(日) ※5月8日(月)は休館です。
- 時間:9:30〜16:30
- 場所:斜里町農業資料等収蔵施設(旧朱円小学校)
- 6日(土)、7日(日)、13日(土)、14日(日13:00 頃に、蓄音機を使ったSPレコードの視聴を行います。
収蔵資料展示「明治・大正の美しい和食器」
四季折々の食材が盛り付けられ、生活に欠かせない存在だった和食器。明治から大正にかけて使われた、縁起が 良く美しい絵柄があしらわれた大皿や重箱を展示します。
- 会期:5月10日(水)〜6月4日(日)
- 場所:博物館本館受付前
- ※この展示の観覧料は無料です。
4月
ロビー展 北方民族博物館移動展
「暖かい」だけじゃない!毛皮と北方民族の多彩な関係
北方地域の諸民族は、衣類を始めとするさまざまな生活必需品の素材として動物の毛皮を活用してきました。また、美しい動物の毛皮は、他地域の交易品としても重要でした。本展示では、北方地域の代表的な動物とその毛皮を取り上げ、 それらがどのように活用されてきたのか、実物資料とともに紹介します。
- 会期:4月19日(水)〜 5月21日(日)
- 会場:交流記念館ホール
- ※この展示の観覧料は無料です。
博物館講座「春の星座観察会」
春の夜空の主役は、星座の中で 一番有名なおおくま座の北斗七星で す。北斗七星のひしゃくの柄から牛かい座、おとめ座につながる「春の大曲線」を探してみましょう。また、ヘルクレス座の球状星団も天体望遠鏡で観察します。西の空にはオリオン座などの冬の星座も見ることができます。
- 日時:4月28日(金)19:30〜20:30※悪天候の場合は29日(日)、30日(日)に延期
- 集合場所:知床博物館交流記念館前
- 講師:合地 信生学芸員
- 参加費:無料
- 申込み:必要
- 申込先:知床博物館(0152)23ー1256
収蔵資料展示 端午の節句「五月人形」
子どもの健康と成長を願う端午の節句。大正から昭和の武者人形、弓太刀や三宝揃などを展示します。
- 会期:4月5日(水)〜 5月7日(日)
- 場所:博物館本館受付前
- ※この展示の観覧料は無料です。
3月
ロビー展「蜃気楼・幻氷写真展〜蜃気楼ハンター星弘之の世界vol.2」
福島県のアマチュア写真家・星弘之さんによる幻氷の写真展を、昨年に引き続き開催します。今回は、流氷の上位蜃気楼「幻氷(げんぴょう)」だけでなく蜃気楼の写真や動画も加えパワーアップしています。蜃気楼は空気の温度差によって遠くの景色が不思議な形に見える現象です。約50年間蜃気楼の撮影を続けている星さんが捉えた決定的瞬間にご注目ください。あわせて、かつて知床博物館に勤務していた佐藤トモ子さんや町内在住の仲間の蜃気楼写真も展示します。
- 会期:3月16日(木)〜 4月6日(木)
- 会場:交流記念館ホール
- ※この展示の観覧料は無料です。
3年ぶりにカフェを開催します「蜃気楼・幻氷カフェ」
写真展に先駆けて、星さん・佐藤さんから蜃気楼と幻氷の魅力をたっぷり語っていただきます。全国各地の最新情報や、蜃気楼の謎の解明など、超レア蜃気楼映像を交えながら紹介します。
- 日時:3月15日(水)18:30〜20:00
- 場所:交流記念館 2F 応接室
- 講師:星弘之(蜃気楼ハンター)・佐藤トモ子(気象予報士、知床蜃気楼・幻氷研究会代表)
- 参加費:大人200円(協力会員無料)
- 定員:13名(要申し込み)
- 申込先:知床博物館(0152-23-1256)
- 特典:写真展の先行観覧可能。
収蔵資料展示「昭和の計算機」
電気や電池を使わず、機械的なカラクリのみで計算をする手廻し式タイガー計算器、歯車で数値を累計し計算する円筒状の小型手廻し式クルタ計算機など、懐かしい昭和の計算機を展示します。
- 日時:3月8日(日)〜 4月2日(日)
- 場所:博物館本館受付前
- ※この展示の観覧料は無料です。
2月
ロビー展「知床の水辺を知る3つの研究」
豊かな自然を有する知床では毎年、様々な調査研究が進められています。その成果の一部は国内外の学会や学術論文などでも紹介されてきました。このロビー展では、【知床の水辺】をフィールドとした3つの研究「カワガラスとサケの密接な関係」「サケ研究の今」「イワウベツ川の魚たち〜今とこれから〜」について収蔵展示を交えながら、展示の中でわかりやすく解説します。知床の自然をより深く知る機会としていただけると幸いです。
- 会期:2月7日(火)〜 3月7日(火)
- 会場:交流記念館ホール
- ※この展示の観覧料は無料です。
講座「歩くスキーで行く神の子池観察会」
伏流水の湧き出し口が青色に見える神の子池へ、道道の入り口から歩くスキーで行きます。森の中を観察しながらの片道1時間の散策ののち、帰りに緑の湯に入って疲れをいやします。
- 日時:2月26日(日)9:00 〜15:00(悪天候の場合は中止)
- 集合場所:博物館本館
- 場所:神の子池他
- 講師:合地学芸員、阿部主任
- 定員:6名※要申し込み
- 参加費:300円(中学生以下・協力会員無料)
- 持ち物:歩くスキー各自持参(B &G 海洋センターで借りれます)、昼食、手ぬぐい、お風呂代(450円、18歳以下140円)、暖かい服装
- 申込先:知床博物館(0152-23-1256)
講座「スノーシューで冬の森を散策しよう」
スノーシューを履いて歩けば、夏では見ることができない動物たちの痕跡や景色を見ることができます。知床の森を一緒に歩いてみませんか。
- 日時:2月12日(日)8:00 〜12:30(悪天候の場合は中止)
- 集合場所:博物館本館
- 場所:ウトロの森(1〜2km程度の散策)
- 講師:臼井学芸員、能勢 峰、能勢 理恵学芸員補
- 定員:5名(小学生以上)※要申し込み
- 参加費:無料(スノーシューはお貸しします)
- 持ち物:スキーウエアー等暖かい服装
- 申込先:知床博物館(0152-23-1256)
資料展示 桃の節句「昭和の雛人形」
1933(昭和8年)に購入された雛人形を展示します。約90年前の雛人形ですが、時代を経てもなお華やかで品のある姿のままで、子どもたちの健やかな成長を見守り続けています。
- 日時:2月5日(日)〜 3月5日(日)
- 場所:博物館本館受付前
- ※この展示の観覧料は無料です。
1月
講座「冬の星座観察会」
冬の星座は明るい星が多く、7つもの一等星が輝いています。また、オリオン座大星雲、プレアデス星団(すばる)、西の空にはアンドロメダ大星雲や木星など有名な星雲・星団も多く見られます。冬の天体を望遠鏡で観察してみましょう。
- 日時:令和5年1月13日(金)18:30〜19:30(悪天候の場合は14日(土)、15日(日)に順延)
- 場所:博物館前庭、天体ドーム室
- 講師:合地学芸員
- 定員:20名、要申込み
- 申込先:知床博物館(0152-23-1256)
- 参加費:無料
※小中学生は送迎をお願いします。上記時間のうち途中参加、退場は自由です。
収蔵資料展示 冬の履き物「雪下駄」
ゴム製の長靴が普及する以前の明治中期〜昭和初期にかけて、北海道では冬の履物として下駄、雪駄、爪甲、深靴などが使用されていました。今回は冬の履物の中から「雪下駄」を紹介します。雪下駄は女性が主に晴れ着の際に履いたものです。おしゃれで工夫の凝らされた冬の履物をぜひご覧ください。
- 会期:令和5年1月4日(水)〜31日(火)
- 場所:博物館本館受付前
- ※この展示の観覧料は無料です。
12月
講座「斜里の小麦でヒンメリをつくろう」
ヒンメリとは麦わらでつくられた北欧フィンランドの伝統的な装飾です。クリスマスの飾りとして用いられることも多いヒンメリ。今回は7月に斜里で収穫された小麦わらでヒンメリをつくります。ぜひご参加ください。
- 日時:12月10日(土)10:00〜12:00
- 場所:交流記念館実習室
- 定員:10名
- 参加費:無料
- 講師:臼井学芸員、加賀田学芸員補
- 申込先:知床博物館(0152-23-1256)
講座「トンボ玉づくり」
ガラス棒をバーナーで溶かし、鉄棒に巻き付けてトンボ玉を作ります。今回は大人の方を中心に、じっくり時間をかけてたくさんのトンボ玉を作り表面にきれいな模様も付けてみましょう。
- 日時:12月18日(日)9時、10時、11時から各1時間
- 場所:交流記念館実習室
- 定員:各時間4名
- 参加費:300円(協力会員、中学生以下無料)
- 参加者:小学生以上
- 講師:合地学芸員
- 申込先:知床博物館(0152-23-1256)
開館記念イベント「もちつき大会(持ち帰りのみ)」
開館記念のもちつき大会を3年ぶりに開催します。例年は記念日(12月28日)に行いますが、参加しやすいように12月25日(日)に実施します。新型コロナ対策のため、ついた餅はその場で食べず、持ち帰りとします。
- 日時:12月25日(日)10:00〜11:30(悪天候の場合は中止)
- 場所:博物館前庭
- 参加費:無料(要申込、協力会員優先受付)
- 定員:60名
- 服装:暖かい服装
- 協力:知床博物館協力会
- 申込先:知床博物館(0152-23-1256)
ロビー展示「写真展 斜里平野」
「景観ハンター」を自称する村田良介さんの写真展です。「天に続く道」をはじめとする斜里平野の絶景を写真で紹介します。今回のテーマは「ドローンに負けない写真を撮れるか‥」とのこと。斜里岳や海別岳からの写真を交えて畑や防風林がつくりだす斜里平野の魅力をご覧ください。
- 会期:12月10日(土)〜1月29日(日)
- 場所:交流記念館ホール
- ※この展示の観覧料は無料です。
収蔵資料展示「大正から昭和の防寒手袋」
大正時代のズックと木綿製、昭和の初め頃のわらで編まれたもの、犬の毛皮を中表にしたものなど、「てっかえし」とも呼ばれていた様々な防寒手袋を展示します。当時の冬の暮らしを想像しながらご覧ください。
- 会期:12月1日(木)〜12月25日(日)
- 場所:博物館本館受付前
- ※この展示の観覧料は無料です。
11月
講演会「研究から見えてきた知床のヒグマのくらし」
市街地への出没や、農作物被害…そんな話題の多いヒグマですが、森の中では木の実を食べ、木陰で眠り、静かにたくましく生きているのだそうです。今回は知床で調査研究を続けてきたお二人からヒグマの調査研究と、それによって見えてきた知床のヒグマの暮らしぶりについてお話ししていただきます。
- 日時 11月26日(土)13:30〜
- 場所 交流記念館ホール
- 講師 白根 ゆり ・ 神保 美渚 (独立行政法人 北海道立総合研究機構)
- 申し込み不要
収蔵資料展示「大正浪漫な山高帽子」
大正時代、西洋文化の影響を受けて新しい流行を取り入れた「モボ・モガ」(モダンボーイ・モダンガールの略)の服装が流行しました。モボのファッションアイテムのひとつである「山高帽子」は、斜里で撮影された当時の写真にも身につけている人がよくみられます。今回は当博物館に収蔵されている山高帽子を展示します。
- 会期 10月26日(水)〜11月27日(日)
- 場所 博物館本館受付前
- ※この展示の観覧は無料です。
講座「皆既月食観察とスマホ撮影」
月が東の空から登り始めると間もなく欠け始め、19時17分に皆既月食が始まります。約1時間30分もの長い間、赤胴色の皆既月食が観察されます。今回は要望の多かったスマホを使って天体望遠鏡で見える月の撮影を行いますので、お持ちの方はぜひスマホをご持参ください。
- 日時 11月8日(火)19:00〜20:30(悪天の場合は中止)
- 集合場所 博物館前
- 講師 合地 信生学芸員
- 服装 暖かい服装
- 申込先 知床博物館(0152−23−1256)
ロビー展「はた織りの会展示」
はた織り会のみなさんが、丁寧に時間をかけて織った作品を交流記念館で展示しています。新作も出品していますので、是非ご覧ください。
- 日時 〜11月19日(土)まで
- 場所 交流記念館ホール
- ※ロビー展の観覧は無料です。
10月
収蔵資料展示「昭和のアコーディオンと楽器」
レトロな装飾の昭和時代に使用されていたアコーディオンなどの楽器を展示します。奏でられる音色を想像しながら是非ご覧ください。
- 会期 9月28日(水)〜10月23日(日)
- 場所 博物館本館受付前
- ※この展示の観覧は無料です。
講座「メノウひろいとメノウみがき」
火山活動の熱水(温泉)が、岩石のすき間で冷やされるとメノウができます。この講座では実際に知床半島(真鯉)でメノウを拾い、博物館に帰ってからそれをきれいに磨きます。
- 日時 10月23日(日)9:00〜12:00
- 集合場所 博物館前集合(悪天候の場合は中止)
- 講師 合地 信生学芸員
要参加申し込み(定員5名)定員に達しました- 参加費:300円
- ※本講座は博物館キッズとの共催講座です。
ロビー展「はた織りの会展示」
はた織り会のみなさんが、丁寧に時間をかけて織った作品を交流記念館で展示しています。新作も出品していますので、是非ご覧ください。
- 日時 〜11月19日(土)まで
- 場所 交流記念館ホール
- ※ロビー展の観覧は無料です。
9月
「斜里村の興りと川端家文書」
葦の芸術原野祭にて開催していた知床博物館移動展「斜里村の興りと川端家文書」を、交流記念館ロビーにて展示します。
明治維新後の法整備に伴って、明治10年頃からこのシャリの地にも行政区や郵便局が設置されました。開拓使や三県一局制など国による様々な試みのなか、最初の斜里郡各村戸長となった川端又三郎氏に関する文書が博物館に寄贈されました。当時の様子とその事実が確認できる川端家文書などを紹介します。
- 会期 8月30日(火)〜9月18日(日)まで
- 場所 知床博物館交流記念館ロビー
収蔵展「昭和の嫁入り道具」
昭和時代に自治会で所有されていて、結婚式に貸し出されていた朱塗酒器(三三九度セット)や嫁入り道具などを展示します。
- 会期 9月1日(木)〜9月25日(日)まで
- 場所 博物館本館受付前
- ※この展示の観覧は無料です。
ロビー展「はた織りの会展示」
はた織りの会のみなさんが、ひとつひとつ丁寧に時間をかけて織った作品を展示します。新作も出展しますのでお楽しみに。
- 会期 9月23日(金)〜11月19日(土)まで
- 場所 知床博物館交流記念館ロビー
- ※この展示の観覧は無料です。
講座「秋の星座と土星観察会」
秋の夜空には明るい1等星がなく、少し寂しい感じがしますが、アンドロメダ大星雲やペルセウス座の二重星団が見られます。アンドロメダ大星雲は双眼鏡でも見ることができますので、探してみましょう。輪を持つ土星や縞模様の木星も天体望遠鏡で観察します。
- 日時 9月23日(金)20:00〜21:00(悪天の場合は9月24日(土)、25日(日)に延期)
- 場所 博物館前に集合
- 講師 合地 信生学芸員
- 要申し込み 知床博物館 23-1256
施設公開「農業資料等収蔵施設」
旧朱円小学校をリニューアルした農業資料等収蔵施設の一般公開を行います。職員室を中心にした展示スペースでは、開墾から畑を耕し、作物を育て、収穫するまでに使われた農機具などを展示しています。収蔵庫として利用している体育館など、普段は見ることのできないバックヤードを見に来てください。
- 日時:9月7日(水) 〜 9 月11日(日)9:00〜16:00
- 場 所::斜里町朱円 32 番地 ( 旧朱円小学校)
- ※観覧料は無料です。
施設公開イベント「斜里農業の変遷についての解説」
農業資料等収蔵施設の一般公開に併せて、博物館協力会会員であり以久科で農家をされていた近藤正純さんによる解説を行います。ぜひご参加ください。
- 日時:9月11日(日) ①10:00〜 ②13:00〜
- 場 所::斜里町朱円 32 番地 ( 旧朱円小学校)
- 参加費:無料
- 申し込み:不要(先着20名まで)
8月
移動展「斜里村の興りと川端家文書」
明治維新後の法整備に伴って、明治10年頃からこのシャリの地にも行政区や郵便局が設置されました。開拓使や三県一局制など国による様々な試みのなか、最初の斜里郡各村戸長となった川端又三郎氏に関する文書が博物館に寄贈されました。当時の様子とその事実が確認できる川端家文書などを紹介します。
- 会期 8月6日(土)〜8月27日(土)まで
- 場所 斜里町旧役場庁舎
- ※本移動展は「葦の芸術原野祭」に併せ開催いたします。入場料は無料です。
収蔵展「昭和の玩具と雑誌」
知床博物館に収蔵されている昭和の玩具と雑誌を展示します。童心を思い起こすレトロで懐かしい玩具や雑誌をぜひご覧ください。
- 会期 7月27日(水)〜8月28日(日)まで
- 場所 博物館本館受付前
- ※この展示の観覧は無料です。
講座「北海道の石でキーホルダーを作ろう」
黒曜石、ジャスパー、ヒスイを磨いてオリジナルのキーホルダーを作ってみましょう。
- 日時 8月27日(土)10:00〜12:00
- 場所 交流記念館実習室
- 講師 合地 信生学芸員
- 参加費 大人400円、中学生以下と協力会員は無料
- 定員 10名
- 要申し込み 知床博物館 23-1256
- 服装等 汚れてもよい服装。事前に爪を切っておいてください。
講座「夏の星座と土星観察会」
こと座のベガ、白鳥座のデネブ、ワシ座のアルタイルを結ぶ夏の大三角形や天の川にある星雲・星団を天体望遠鏡で観察します。また、輪を持つ土星も見てみましょう。
- 日時 8月2日(火)20:00〜21:00(悪天の場合は8月3日(水)に変更)
- 場所 博物館前に集合
- 講師 合地 信生学芸員
- 要申し込み 知床博物館 23-1256
早朝草取りボランティア
6〜10月に実施しているボランティア草取りを今年も行います。よろしければご参加ください。
- 日時 8月10日(水)6:00〜7:00(雨天中止)
- 場所 高山植物園(博物館裏のワシ小屋付近)
- 持ち物 帽子、軍手、虫除け
夏休み講座「磯場の生き物採集観察会」悪天候の為中止
チャシコツ崎でたも網を使って魚や貝などの磯の生き物を捕まえて観察します。
- 日時 8月2日(火)8:30〜12:00
- 場所 博物館前に集合 チャシコツ崎へ
- 対象 小学生3年生から中学3年生
- 定員 12人
- 服装・持ち物 長袖、長ズボン、帽子、長めの靴下、タオル、着替え、飲み物
- 要申し込み 知床博物館 23-1256
夏休み講座「斜里の魚をさばいて食べよう」
斜里周辺の海でさばいて魚をさばいて、焼いたり煮たりして食べます。
- 日時 8月3日(水)9:00〜12:00
- 集合 博物館 交流記念館ロビー
- 対象 小学生4年生から中学3年生
- 定員 10人
- 服装・持ち物 汚れてもよい服、軍手、飲み物
- 要申し込み 知床博物館 23-1256
夏休み講座「はたおり体験」
所要時間は一人30分くらいです。初めての人もゆっくり織ることができます。
- 日時 8月4日(木)9:30〜14:30のうち30分
- 場所 博物館 交流記念館ロビー
- 対象 小学生1年生から中学3年生
- 定員 20人
- 指導 はたおりの会
- 要申し込み 知床博物館 23-1256
夏休み講座「トンボ玉つくり体験」
炎でガラスを溶かし、トンボ玉(ガラス玉)を作ります。所要時間は一人30分です。
- 日時 8月5日(金)9:00〜12:00のうち30分
- 集合 博物館 交流記念館ロビー
- 対象 小学生3年生から中学3年生
- 定員 12人
- 要申し込み 知床博物館 23-1256
7月
ロビー展「学校の変遷」関連イベント ギャラリートーク&懐かしのミニコンサート
現在交流記念館ホールで開催しているロビー展「学校の変遷」の資料を見ながら学校の歴史を解説します。 また校歌のミニコンサート(ピアノ) を行います。
- 日時 7月9日(土)10:00〜11:30
- 場所 交流記念館ホール
- 講師 村田 良介学芸員、加賀田 直子(ピアノ)
- 定員 20名程度(要申し込み 知床博物館 23-1256)
観察会「斜里平野地質観察会」
屈斜路火山の火砕流と豊かな水 量の斜里川で作られた斜里平野。 中斜里の採石場、来運の湧水、さくらの滝、神の子池、摩周カルデラ、小清水原生花園の鳴き砂などを観察し、斜里平野の成り立ちについて考えてみましょう。
- 日時 7月23日(土)9:00〜16:00まで(悪天候の場合は7月24日(日)に延期)
- 集合場所 博物館前庭
- 講師 合地 信生(知床博物館学芸員)
- 持ち物 雨具、長靴、お弁当、筆記用具
- 参加人数 7名(要参加申込、高校生以上)
- 参加費 300円(協力会員無料)
収蔵展「しれとこ斜里ねぷた小物」
1983(昭和58)年7月、弘前市との友好都市盟約を記念して「弘前ねぷた」が初めて斜里で出陣しました。今回はしれとこ斜里ねぷたに関する小物を展示します。
- 会期 6月29日(水)〜7月24日(日)
- 場所 博物館本館受付前
- ※この展示の観覧は無料です。
早朝草取りボランティア
6月から10月まで、毎月10日に実施していきます。よろしければご参加ください。
- 日時 7月10日(日)6:00〜7:00(雨天中止)
- 場所 高山植物園(博物館裏のワシ小屋付近)
- 持ち物 帽子、軍手、虫除け
- 申し込みは不要(当日、現地にお越しください。)
6月
知床博物館ロビー展「学校の変遷」
斜里町の学校は明治25年(130年前)の斜里尋常小学校の設置が始まりです。昭和20年代には小学校15校、中学校11校がありましたが、現在は小学校2校、中学校1校、小中一貫の義務教育学校1校です。学校の変遷を産業や人口の変化と併せて紹介します。
- 会期 6月28日(火)〜8月21日(日)まで
- 場所 交流記念館ホール
- 主催 知床博物館
- ※この展示の観覧は無料です。
収蔵資料展示「昭和レトロなかき氷製造機」
本体に描かれた人工衛星や天体望遠鏡が当時の時代背景を感じさせます。
- 会期 5月25日(水)〜6月26日(日)
- 場所 博物館本館受付前
- ※本展示のみの観覧は無料です。
観察会「知床半島一周 地質観察会」
最近、羅臼側で地質観察会をする機会が多くなり、斜里川も含めた知床半島全体の火山活動の歴史が明らかになってきました。斜里川から羅臼側へと車で移動しながら、半島の両側で火山活動がどのように起こったのかを観察します。
- 日時 6月25日(土)8:30〜16:30まで
- 集合場所 博物館前庭
- 講師 合地 信生(知床博物館学芸員)
- 持ち物 雨具、長靴、お弁当、筆記用具
- 参加人数 7名(要参加申込、高校生以上)
- 参加費 300円(協力会員無料)
- ※この展示の観覧は無料です。
博物館みどりの日 花壇に花を植えにきませんか?
知床博物館みどりの日では毎年、博物館駐車場脇の花壇に、たくさんの花を植え、来館者を迎えてきました。今年度も下記の通り実施します。ご都合のよろしい方はぜひご参加ください。
- 日時 6月26日(日)10:00〜12:00
- 場所 博物館前庭
- 持ち物 帽子、軍手、虫除け
- 申し込みは不要(当日、現地にお越しください。)
高山植物園 草取りボランティアが始まります
今年も、博物館裏にある高山植物園の草取りボランティア活動が始まります。朝の涼しい時間に、色とりどりの草花を眺めながら作業をしてみませんか。6月から10月まで、毎月10日に実施していきます。ぜひご都合のつく日にご参加ください。
- 日時 6月10日(金)6:00〜7:00(雨天中止)
- 場所 高山植物園(博物館裏のワシ小屋付近)
- 持ち物 帽子、軍手、虫除け
- 申し込みは不要(当日、現地にお越しください。)
5月
ギャラリートーク
北海道立北方民族博物館の学芸員が移動展の展示解説に加え、ユーラシア大陸北部の遊牧文化についてお話します。
- 日時 5月14日(土)13:00〜14:00頃まで
- 場所 交流記念館ホール
- 講師 中田 篤(北方民族博物館学芸員)
- 参加人数 15名程度(要申し込み)
- 参加費 無料
観察会「斜里ーウトロ地質観察会」
博物館で作成し、YouTubeで配信したおうちでブラ合地「知床の石➀」の地質ポイントを現地でより詳しく観察します。今回の観察テーマはマグマの深い場所から浅い場所への移動です。また、チャシコツ崎(カメ岩)のでき方についても考えてみます。
- 日時 5月28日(土)8:30〜12:00頃まで 雨天時は 29日(日)に延期
- 場所 博物館前庭集合
- 講師 合地 信生学芸員
- 参加人数 7名(要申し込み)
- 持ち物 雨具、長靴、筆記用具
- 参加費 300円(中学生以下、協力会会員無料)
4月
北方民族博物館移動展「トナカイと暮らす̶タイガの遊牧民たち」
ユーラシア大陸北部で広く先住民の生業として営まれてきたトナカイ遊牧は、自然環境や携わる民族集団によって地域ごとに多様な展開をみせてきました。この展示では、シベリア東部から南部にかけてのタイガ地域に広がるトナカイ遊牧文化について紹介します。
- 会期 4月27日(水)~ 6月19日(日)まで
- 主催 北海道立北方民族博物館・知床博物館
- 場所 交流記念館ホール
収蔵資料展示「アンティークな手回し式ミシン」
足踏み式が主流になる前の、昭和初期に製造された手回しミシンを展示します。丸みのあるボデイ、ロゴのデザイン、模様など細部にこだわりがあり、アンティークな雰囲気を醸し出しています。
- 会期 3月19日(土)~5月22日(日)
- 場所 本館受付前
※この展示の観覧は無料です。
3月
おうちで楽しむブラ合地 第 1 弾!「知床の石・いろいろ!」
合地学芸員の地質観察会を、今回は配信によりおうちでお楽しみいただけます!知床半島は、峰浜付
近の半島基部の海岸線に堆積岩、それから先端部にかけての海岸線に海底火山活動の地層、そして半島の中軸部には陸上火山活動の岩石があります。第1弾として、1. 野外での露頭観察、2. 手にとっての観察、3. 顕微鏡での観察、4. そのでき方について、写真や図を用いて解説します。
- 配信日 3月25日(金)~5月末
- 配信方法 視聴希望者にYoutubeの期間限定URLをメールでお送りします。
- 申込方法 件名を「配信希望」とし、お名前、電話番号を明記の上、博物館へメール(shiretoko-m@sea.plala.or.jp) してください。難しい場合は博物館へ電話にてお申し込みください。
ロビー展「幻氷写真展~蜃気楼ハンター 星弘之の世界~」
40年来「蜃気楼ハンター」として蜃気楼の研究や撮影を続けているアマチュア写真家・星弘之さんによる幻氷の写真展を開催します。
斜里町を中心としたオホーツクエリアでは、流氷が海岸を離れていく春先、めずらしい流氷の上位蜃気楼「幻氷(げんぴょう)」が現れます。幻氷の魅力に取りつかれ、ほぼ毎春、星さんが斜里町に長期滞在して捉えた決定的瞬間を展示します。
会場のモニターでは、迫力ある動きの幻氷動画や、斜里近辺の仲間(知床蜃気楼・幻氷研究会)が撮影した写真もご紹介します。ぜひこの機会にお立ち寄りください。
- 会期 3月16日(水)~4月6日(水)
- 場所 交流記念館ホール
2月
流氷観察会
冬のオホーツク海の魅力のひとつに流氷があります。浜でとった流氷や”つらら”、洗面器で凍らせた氷の結晶をノコギリで切断したり、偏光板を使って観察したりして、その出来かたを考えます。海岸ではクリオネが見えるかもしれません!
- 日時 2月19日(土)10:00~11:30
- 場所 博物館実習室、前浜
- 講師 合地学芸員
- 服装 暖かい格好(帽子、手袋など)
- 定員 15名
今から90年前のひな人形
今から約90年前の1933(昭和8)年に購入されたひな人形を展示します。時代を経てもその華やかさを今に伝えています。今回は昭和の羽子板も合わせて展示します。ひな人形は、災厄を人形にのせて川に流す行事と人形遊びが結びついたものと考えられています。羽子板も邪気払いの意味があるとされ、健康を願う気持ちにつながるといえるでしょう。
- 会期 2月1日(火)~3月15日(火)
- 場所 本館受付前
1月
ロビー展 樺太(絵ハガキに見る樺太の記憶~知られざる北の国境)
日本が統治していた時代の樺太(サハリン)で販売されていた絵葉書を展示します。当時のサハリンの街並みや森林、動物といった自然の様子など、当時のさまざまな風景を伺い知ることができます。
- 期間: ~令和4年1月30日(日)
- 場所:交流記念館ホール
厳寒の天体観察会
冬の星座は明るい星が多く、7つもの1等星が輝いています。またオリオン座大星雲、プレアデス星団(すばる)、西の空にはアンドロメダ大星雲など有名な星雲・星団も多く見られます。冬の天体を望遠鏡で観察してみましょう。
- 日時:令和4年1月21日(金)18:30~19:30、
- 悪天候の場合は22、23日に順延
- 場所:博物館前庭、天体ドーム室
- 講師:村上館長、合地学芸員
- 定員:20名
- ※小中学生は送迎をお願いします。上記時間のうち途中加参加、退場は自由
博物館カフェ「アイヌ語地名から探る絶滅危惧種カワシンジュガイの棲む川!」
カワシンジュガイという川に棲む二枚貝を見たことがありますか?この貝は、綺麗な川にしか棲めな
いことから、棲む川を特定することで現在の川の環境を伺い知ることができます。北海道に残るアイヌ
語地名には、このカワシンジュガイとその仲間の貝を意味する地名が数多く残っています。では、北海
道のどこにどれくらい地名が残っているのでしょうか?地名の残る川には現在もこの貝が暮らすので
しょうか?今年度行った現地調査の様子や結果を、写真や映像を用いて、三浦学芸員がご紹介します!
- 日時:令和4年1月20日(木)18:30~19:30
- 場所:交流記念館2F会議室
- 定員:15名、要申込、参加無料
- ※中学生以上対象を想定しています。
化石レプリカづくり体験!(博物館キッズ拡大版)
大昔に生きていたアンモナイトの化石レプリカを石膏を使って作ってみます!
- 日時:令和4年1月16日(日)9:00~11:30
- 場所:交流記念館2F実習室
- 定員:5名、要申込、参加無料、小3以上対象
9月
「斜里村の興りと川端家文書」
葦の芸術原野祭にて開催していた知床博物館移動展「斜里村の興りと川端家文書」を、交流記念館ロビーにて展示します。
明治維新後の法整備に伴って、明治10年頃からこのシャリの地にも行政区や郵便局が設置されました。開拓使や三県一局制など国による様々な試みのなか、最初の斜里郡各村戸長となった川端又三郎氏に関する文書が博物館に寄贈されました。当時の様子とその事実が確認できる川端家文書などを紹介します。
- 会期 8月30日(火)〜9月18日(日)まで
- 場所 知床博物館交流記念館ロビー
収蔵展「昭和の嫁入り道具」
昭和時代に自治会で所有されていて、結婚式に貸し出されていた朱塗酒器(三三九度セット)や嫁入り道具などを展示します。
- 会期 9月1日(木)〜9月25日(日)まで
- 場所 博物館本館受付前
- ※この展示の観覧は無料です。
ロビー展「はた織りの会展示」
はた織りの会のみなさんが、ひとつひとつ丁寧に時間をかけて織った作品を展示します。新作も出展しますのでお楽しみに。
- 会期 9月23日(金)〜11月19日(土)まで
- 場所 知床博物館交流記念館ロビー
- ※この展示の観覧は無料です。
講座「秋の星座と土星観察会」
秋の夜空には明るい1等星がなく、少し寂しい感じがしますが、アンドロメダ大星雲やペルセウス座の二重星団が見られます。アンドロメダ大星雲は双眼鏡でも見ることができますので、探してみましょう。輪を持つ土星や縞模様の木星も天体望遠鏡で観察します。
- 日時 9月23日(金)20:00〜21:00(悪天の場合は9月24日(土)、25日(日)に延期)
- 場所 博物館前に集合
- 講師 合地 信生学芸員
- 要申し込み 知床博物館 23-1256
施設公開「農業資料等収蔵施設」
旧朱円小学校をリニューアルした農業資料等収蔵施設の一般公開を行います。職員室を中心にした展示スペースでは、開墾から畑を耕し、作物を育て、収穫するまでに使われた農機具などを展示しています。収蔵庫として利用している体育館など、普段は見ることのできないバックヤードを見に来てください。
- 日時:9月7日(水) 〜 9 月11日(日)9:00〜16:00
- 場 所::斜里町朱円 32 番地 ( 旧朱円小学校)
- ※観覧料は無料です。
施設公開イベント「斜里農業の変遷についての解説」
農業資料等収蔵施設の一般公開に併せて、博物館協力会会員であり以久科で農家をされていた近藤正純さんによる解説を行います。ぜひご参加ください。
- 日時:9月11日(日) ①10:00〜 ②13:00〜
- 場 所::斜里町朱円 32 番地 ( 旧朱円小学校)
- 参加費:無料
- 申し込み:不要(先着20名まで)
8月
移動展「斜里村の興りと川端家文書」
明治維新後の法整備に伴って、明治10年頃からこのシャリの地にも行政区や郵便局が設置されました。開拓使や三県一局制など国による様々な試みのなか、最初の斜里郡各村戸長となった川端又三郎氏に関する文書が博物館に寄贈されました。当時の様子とその事実が確認できる川端家文書などを紹介します。
- 会期 8月6日(土)〜8月27日(土)まで
- 場所 斜里町旧役場庁舎
- ※本移動展は「葦の芸術原野祭」に併せ開催いたします。入場料は無料です。
収蔵展「昭和の玩具と雑誌」
知床博物館に収蔵されている昭和の玩具と雑誌を展示します。童心を思い起こすレトロで懐かしい玩具や雑誌をぜひご覧ください。
- 会期 7月27日(水)〜8月28日(日)まで
- 場所 博物館本館受付前
- ※この展示の観覧は無料です。
講座「北海道の石でキーホルダーを作ろう」
黒曜石、ジャスパー、ヒスイを磨いてオリジナルのキーホルダーを作ってみましょう。
- 日時 8月27日(土)10:00〜12:00
- 場所 交流記念館実習室
- 講師 合地 信生学芸員
- 参加費 大人400円、中学生以下と協力会員は無料
- 定員 10名
- 要申し込み 知床博物館 23-1256
- 服装等 汚れてもよい服装。事前に爪を切っておいてください。
講座「夏の星座と土星観察会」
こと座のベガ、白鳥座のデネブ、ワシ座のアルタイルを結ぶ夏の大三角形や天の川にある星雲・星団を天体望遠鏡で観察します。また、輪を持つ土星も見てみましょう。
- 日時 8月2日(火)20:00〜21:00(悪天の場合は8月3日(水)に変更)
- 場所 博物館前に集合
- 講師 合地 信生学芸員
- 要申し込み 知床博物館 23-1256
早朝草取りボランティア
6〜10月に実施しているボランティア草取りを今年も行います。よろしければご参加ください。
- 日時 8月10日(水)6:00〜7:00(雨天中止)
- 場所 高山植物園(博物館裏のワシ小屋付近)
- 持ち物 帽子、軍手、虫除け
夏休み講座「磯場の生き物採集観察会」悪天候の為中止
チャシコツ崎でたも網を使って魚や貝などの磯の生き物を捕まえて観察します。
- 日時 8月2日(火)8:30〜12:00
- 場所 博物館前に集合 チャシコツ崎へ
- 対象 小学生3年生から中学3年生
- 定員 12人
- 服装・持ち物 長袖、長ズボン、帽子、長めの靴下、タオル、着替え、飲み物
- 要申し込み 知床博物館 23-1256
夏休み講座「斜里の魚をさばいて食べよう」
斜里周辺の海でさばいて魚をさばいて、焼いたり煮たりして食べます。
- 日時 8月3日(水)9:00〜12:00
- 集合 博物館 交流記念館ロビー
- 対象 小学生4年生から中学3年生
- 定員 10人
- 服装・持ち物 汚れてもよい服、軍手、飲み物
- 要申し込み 知床博物館 23-1256
夏休み講座「はたおり体験」
所要時間は一人30分くらいです。初めての人もゆっくり織ることができます。
- 日時 8月4日(木)9:30〜14:30のうち30分
- 場所 博物館 交流記念館ロビー
- 対象 小学生1年生から中学3年生
- 定員 20人
- 指導 はたおりの会
- 要申し込み 知床博物館 23-1256
夏休み講座「トンボ玉つくり体験」
炎でガラスを溶かし、トンボ玉(ガラス玉)を作ります。所要時間は一人30分です。
- 日時 8月5日(金)9:00〜12:00のうち30分
- 集合 博物館 交流記念館ロビー
- 対象 小学生3年生から中学3年生
- 定員 12人
- 要申し込み 知床博物館 23-1256
7月
ロビー展「学校の変遷」関連イベント ギャラリートーク&懐かしのミニコンサート
現在交流記念館ホールで開催しているロビー展「学校の変遷」の資料を見ながら学校の歴史を解説します。 また校歌のミニコンサート(ピアノ) を行います。
- 日時 7月9日(土)10:00〜11:30
- 場所 交流記念館ホール
- 講師 村田 良介学芸員、加賀田 直子(ピアノ)
- 定員 20名程度(要申し込み 知床博物館 23-1256)
観察会「斜里平野地質観察会」
屈斜路火山の火砕流と豊かな水 量の斜里川で作られた斜里平野。 中斜里の採石場、来運の湧水、さくらの滝、神の子池、摩周カルデラ、小清水原生花園の鳴き砂などを観察し、斜里平野の成り立ちについて考えてみましょう。
- 日時 7月23日(土)9:00〜16:00まで(悪天候の場合は7月24日(日)に延期)
- 集合場所 博物館前庭
- 講師 合地 信生(知床博物館学芸員)
- 持ち物 雨具、長靴、お弁当、筆記用具
- 参加人数 7名(要参加申込、高校生以上)
- 参加費 300円(協力会員無料)
収蔵展「しれとこ斜里ねぷた小物」
1983(昭和58)年7月、弘前市との友好都市盟約を記念して「弘前ねぷた」が初めて斜里で出陣しました。今回はしれとこ斜里ねぷたに関する小物を展示します。
- 会期 6月29日(水)〜7月24日(日)
- 場所 博物館本館受付前
- ※この展示の観覧は無料です。
早朝草取りボランティア
6月から10月まで、毎月10日に実施していきます。よろしければご参加ください。
- 日時 7月10日(日)6:00〜7:00(雨天中止)
- 場所 高山植物園(博物館裏のワシ小屋付近)
- 持ち物 帽子、軍手、虫除け
- 申し込みは不要(当日、現地にお越しください。)
6月
知床博物館ロビー展「学校の変遷」
斜里町の学校は明治25年(130年前)の斜里尋常小学校の設置が始まりです。昭和20年代には小学校15校、中学校11校がありましたが、現在は小学校2校、中学校1校、小中一貫の義務教育学校1校です。学校の変遷を産業や人口の変化と併せて紹介します。
- 会期 6月28日(火)〜8月21日(日)まで
- 場所 交流記念館ホール
- 主催 知床博物館
- ※この展示の観覧は無料です。
収蔵資料展示「昭和レトロなかき氷製造機」
本体に描かれた人工衛星や天体望遠鏡が当時の時代背景を感じさせます。
- 会期 5月25日(水)〜6月26日(日)
- 場所 博物館本館受付前
- ※本展示のみの観覧は無料です。
観察会「知床半島一周 地質観察会」
最近、羅臼側で地質観察会をする機会が多くなり、斜里川も含めた知床半島全体の火山活動の歴史が明らかになってきました。斜里川から羅臼側へと車で移動しながら、半島の両側で火山活動がどのように起こったのかを観察します。
- 日時 6月25日(土)8:30〜16:30まで
- 集合場所 博物館前庭
- 講師 合地 信生(知床博物館学芸員)
- 持ち物 雨具、長靴、お弁当、筆記用具
- 参加人数 7名(要参加申込、高校生以上)
- 参加費 300円(協力会員無料)
- ※この展示の観覧は無料です。
博物館みどりの日 花壇に花を植えにきませんか?
知床博物館みどりの日では毎年、博物館駐車場脇の花壇に、たくさんの花を植え、来館者を迎えてきました。今年度も下記の通り実施します。ご都合のよろしい方はぜひご参加ください。
- 日時 6月26日(日)10:00〜12:00
- 場所 博物館前庭
- 持ち物 帽子、軍手、虫除け
- 申し込みは不要(当日、現地にお越しください。)
高山植物園 草取りボランティアが始まります
今年も、博物館裏にある高山植物園の草取りボランティア活動が始まります。朝の涼しい時間に、色とりどりの草花を眺めながら作業をしてみませんか。6月から10月まで、毎月10日に実施していきます。ぜひご都合のつく日にご参加ください。
- 日時 6月10日(金)6:00〜7:00(雨天中止)
- 場所 高山植物園(博物館裏のワシ小屋付近)
- 持ち物 帽子、軍手、虫除け
- 申し込みは不要(当日、現地にお越しください。)
5月
ギャラリートーク
北海道立北方民族博物館の学芸員が移動展の展示解説に加え、ユーラシア大陸北部の遊牧文化についてお話します。
- 日時 5月14日(土)13:00〜14:00頃まで
- 場所 交流記念館ホール
- 講師 中田 篤(北方民族博物館学芸員)
- 参加人数 15名程度(要申し込み)
- 参加費 無料
観察会「斜里ーウトロ地質観察会」
博物館で作成し、YouTubeで配信したおうちでブラ合地「知床の石➀」の地質ポイントを現地でより詳しく観察します。今回の観察テーマはマグマの深い場所から浅い場所への移動です。また、チャシコツ崎(カメ岩)のでき方についても考えてみます。
- 日時 5月28日(土)8:30〜12:00頃まで 雨天時は 29日(日)に延期
- 場所 博物館前庭集合
- 講師 合地 信生学芸員
- 参加人数 7名(要申し込み)
- 持ち物 雨具、長靴、筆記用具
- 参加費 300円(中学生以下、協力会会員無料)
4月
北方民族博物館移動展「トナカイと暮らす̶タイガの遊牧民たち」
ユーラシア大陸北部で広く先住民の生業として営まれてきたトナカイ遊牧は、自然環境や携わる民族集団によって地域ごとに多様な展開をみせてきました。この展示では、シベリア東部から南部にかけてのタイガ地域に広がるトナカイ遊牧文化について紹介します。
- 会期 4月27日(水)~ 6月19日(日)まで
- 主催 北海道立北方民族博物館・知床博物館
- 場所 交流記念館ホール
収蔵資料展示「アンティークな手回し式ミシン」
足踏み式が主流になる前の、昭和初期に製造された手回しミシンを展示します。丸みのあるボデイ、ロゴのデザイン、模様など細部にこだわりがあり、アンティークな雰囲気を醸し出しています。
- 会期 3月19日(土)~5月22日(日)
- 場所 本館受付前
※この展示の観覧は無料です。
3月
おうちで楽しむブラ合地 第 1 弾!「知床の石・いろいろ!」
合地学芸員の地質観察会を、今回は配信によりおうちでお楽しみいただけます!知床半島は、峰浜付
近の半島基部の海岸線に堆積岩、それから先端部にかけての海岸線に海底火山活動の地層、そして半島の中軸部には陸上火山活動の岩石があります。第1弾として、1. 野外での露頭観察、2. 手にとっての観察、3. 顕微鏡での観察、4. そのでき方について、写真や図を用いて解説します。
- 配信日 3月25日(金)~5月末
- 配信方法 視聴希望者にYoutubeの期間限定URLをメールでお送りします。
- 申込方法 件名を「配信希望」とし、お名前、電話番号を明記の上、博物館へメール(shiretoko-m@sea.plala.or.jp) してください。難しい場合は博物館へ電話にてお申し込みください。
ロビー展「幻氷写真展~蜃気楼ハンター 星弘之の世界~」
40年来「蜃気楼ハンター」として蜃気楼の研究や撮影を続けているアマチュア写真家・星弘之さんによる幻氷の写真展を開催します。
斜里町を中心としたオホーツクエリアでは、流氷が海岸を離れていく春先、めずらしい流氷の上位蜃気楼「幻氷(げんぴょう)」が現れます。幻氷の魅力に取りつかれ、ほぼ毎春、星さんが斜里町に長期滞在して捉えた決定的瞬間を展示します。
会場のモニターでは、迫力ある動きの幻氷動画や、斜里近辺の仲間(知床蜃気楼・幻氷研究会)が撮影した写真もご紹介します。ぜひこの機会にお立ち寄りください。
- 会期 3月16日(水)~4月6日(水)
- 場所 交流記念館ホール
2月
流氷観察会
冬のオホーツク海の魅力のひとつに流氷があります。浜でとった流氷や”つらら”、洗面器で凍らせた氷の結晶をノコギリで切断したり、偏光板を使って観察したりして、その出来かたを考えます。海岸ではクリオネが見えるかもしれません!
- 日時 2月19日(土)10:00~11:30
- 場所 博物館実習室、前浜
- 講師 合地学芸員
- 服装 暖かい格好(帽子、手袋など)
- 定員 15名
今から90年前のひな人形
今から約90年前の1933(昭和8)年に購入されたひな人形を展示します。時代を経てもその華やかさを今に伝えています。今回は昭和の羽子板も合わせて展示します。ひな人形は、災厄を人形にのせて川に流す行事と人形遊びが結びついたものと考えられています。羽子板も邪気払いの意味があるとされ、健康を願う気持ちにつながるといえるでしょう。
- 会期 2月1日(火)~3月15日(火)
- 場所 本館受付前
1月
ロビー展 樺太(絵ハガキに見る樺太の記憶~知られざる北の国境)
日本が統治していた時代の樺太(サハリン)で販売されていた絵葉書を展示します。当時のサハリンの街並みや森林、動物といった自然の様子など、当時のさまざまな風景を伺い知ることができます。
- 期間: ~令和4年1月30日(日)
- 場所:交流記念館ホール
厳寒の天体観察会
冬の星座は明るい星が多く、7つもの1等星が輝いています。またオリオン座大星雲、プレアデス星団(すばる)、西の空にはアンドロメダ大星雲など有名な星雲・星団も多く見られます。冬の天体を望遠鏡で観察してみましょう。
- 日時:令和4年1月21日(金)18:30~19:30、
- 悪天候の場合は22、23日に順延
- 場所:博物館前庭、天体ドーム室
- 講師:村上館長、合地学芸員
- 定員:20名
- ※小中学生は送迎をお願いします。上記時間のうち途中加参加、退場は自由
博物館カフェ「アイヌ語地名から探る絶滅危惧種カワシンジュガイの棲む川!」
カワシンジュガイという川に棲む二枚貝を見たことがありますか?この貝は、綺麗な川にしか棲めな
いことから、棲む川を特定することで現在の川の環境を伺い知ることができます。北海道に残るアイヌ
語地名には、このカワシンジュガイとその仲間の貝を意味する地名が数多く残っています。では、北海
道のどこにどれくらい地名が残っているのでしょうか?地名の残る川には現在もこの貝が暮らすので
しょうか?今年度行った現地調査の様子や結果を、写真や映像を用いて、三浦学芸員がご紹介します!
- 日時:令和4年1月20日(木)18:30~19:30
- 場所:交流記念館2F会議室
- 定員:15名、要申込、参加無料
- ※中学生以上対象を想定しています。
化石レプリカづくり体験!(博物館キッズ拡大版)
大昔に生きていたアンモナイトの化石レプリカを石膏を使って作ってみます!
日時:3月30日(土)9:00〜12:00
- 日時:令和4年1月16日(日)9:00~11:30
- 場所:交流記念館2F実習室
- 定員:5名、要申込、参加無料、小3以上対象
2月
ロビー展 姉妹町盟約50周年記念「竹富町との交流のあゆみ写真展」
竹富町との姉妹町盟約の調印は昭和48 年 (1973)1月10日。その後は農業や漁業の交流、物産展の開催、児童・生徒や町民号による相互訪問などが続いています。これら半世紀にわたる交流を写真で振り返ります。
- 会期:2月1日(木)〜22日木)
- 場所:交流記念館 ロビー
- ロビー展のみの観覧は無料です。
ミュージアムカフェ 姉妹町盟約50周年記念 「カフェ種子取(たなどぅい)祭」
竹富島の種子取祭は五穀豊穣を願う伝統的な農耕儀礼で、毎年旧暦の9月から10月頃に9日間にわたって行われ、7日目と8日目には芸能が奉納されます。国の重要無形民俗文化財。お茶しながら、赤瓦民家や展示資料に囲まれて姉妹町の祭りや生活のお話を聞きます。
- 日時:2月22日(木)18:30〜20:00
- 場所:交流記念館 展示室赤瓦民家前
- 参加費:大人200円(協力会員は無料)
- 定員:先着20名(要申込み)
- 講師:飯田泰彦 町史編集係長(竹富町教育委員会町社会文課)他
- 申込先:知床博物館 (0152)23-1256
収蔵資料展示 「御殿飾りの雛人形」
3月3日の桃の節句に合わせ、段飾りとはちょっと違う、建物付きの雛人形を展示します。宮殿のような建物にお内裏様とお雛様が並ぶ「御殿飾り」は 、江戸時代に生まれ 、西日本を中心に昭和30年代まで流行しました。斜里町富士で飾られた雅な雛人形をご覧ください。
- 会期:2月7日(水)〜 3月3日(日)
- 場所:博物館本館受付前
- この展示の観覧料は無料です。
ロビー展 道東地区博物館巡回展「カメラは見た!動物たちの素顔」
普段見なれた動物たちを「ちょっと変わった角度」からとらえた写真展です。一瞬の気を抜いた時の表情や撮影した地域ならではの動物たちの風景など、いつもと違った動物たちの素顔をお楽しみください。※本内容は美幌博物館特別展の内容を巡回展として再構成したものとなっています。
- 会期:2月27日(火)〜3月31日(日)
- 場所:交流記念館ロビー
- ロビー展のみの観覧は無料です。
1月
ロビー展「地図・ちず・マップの世界」
知床博物館で所有している地図を紹介します。見れば見るほど「沼」にはまる地図の世界。学校で使った地図、ロシア語の地図、5 万分の1地形図から斜里市街図、古地図などを展示します。
- 会期:1月10日(水)~28日(日)
- 場所:交流記念館 ロビー
- ロビー展のみの観覧は無料です。
ミュージアムカフェ「地図カフェ」
ロビー展で展示する地図をはじめ、講師が最近気になる地図事情について、お茶しながら気軽にトークします。
- 日時:1月27日 ( 土 )18:30〜20:00
- 場所:交流記念館 2階応接室
- 参加費:大人 200 円 ( 協力会員無料 )
- 定員:先着14 名(要申込み)
- 講師:村田 良介 学芸員
- 申込先:知床博物館 (0152)23-1256
収蔵資料展示 冬の防寒着 角巻
寒さが厳しい冬の間、明治から昭和にかけて使われた角巻は、嫁入り道具としても扱われた高級品でした。昭和15(1940)年ごろ、富士在住の女性が斜里のまちで購入した角巻から、当時の冬のおしゃれを感じてください。
- 会期:1月4日(木)〜 2月4日(日)
- 場所:博物館本館受付前
- この展示の観覧料は無料です。
講座「冬の星座観察会」
冬の星座には恒星で一番明るいシリウスなど明るく輝く一等星が7つもあり、有名なオリオン座も冬の夜空を飾っています。また、星の誕生を教えてくれるすばるやオリオン座大星雲を天体望遠鏡で観察します。
- 日時:1月12日(金) 19:00〜20:00(悪天候の場合は13日(土)か14日(日)に変更)
- 場所:博物館前庭と天体ドーム室
- 申込み:必要
- 申込先:知床博物館 (0152)23-1256
- 参加費:無料
- 服装:防寒具
- 講師:合地 信生 学芸員
講座 親子参歓迎!「お絵かき巣箱作り」
自然豊かな斜里町では市街地でも様々な野鳥が子育てをしていま す。野鳥の「巣作りから子育て」を観察するための巣箱を一緒に作ってみませんか。できあがった巣箱にはお絵かきをして博物館の裏庭に仕掛けます。参加者は、来年から巣箱を開けて中の様子を観察できます。モモンガやリスも入るかも!
- 日時:1月20日(土)9:00 〜12:00
- 場所:交流記念館実習室
- 対象:小・中学生(小学3年生以下は要保護者同伴)
- 参加費:無料
- 定員:15組
- 持ち物:暖かい服装、軍手
- 講師:臼井 平 学芸員
- 申込み:必要
- 申込先:知床博物館 (0152)23-1256
12月
ミュージアムカフェ「カフェ斜里平野」
特別展「斜里平野の魅力」の会期終了が迫っています。展示や図録では触れていないことや斜里平野の魅力をスライドや地図を見ながら語り合います。お茶しながら、あらためて魅力を再発見しましょう!
- 日時:12月15日(金) 18:30〜20:00
- 場所:交流記念館 2F 応接室
- 講師:村田良介学芸員
- 参加費:大人 200 円(協力会員無料)
- 定員:先着14 名(要申込み)
- 申込先:知床博物館 (0152)23-1256
- 18:00 〜18:30 にギャラリートーク (展示解説)を行います(無料)。特別展は12月17日(日)まで。
講座「北海道の石でキーホルダー作り」
北海道には黒曜石の産地白滝、羅臼と留辺蘂にはジャスパー、旭川神居古潭にはヒスイなど魅力的な石が産出します。研磨機を使ってオリジナルのキーホルダーを作ってみましょう。
- 日時:12 月16 日(土)10:00 〜12:00
- 場所:交流記念館実習室
- 参加費:400円(中学生以下と協力会員は無料)
- 定員:10 名(要申込み)
- 申込先:知床博物館 (0152)23-1256
- 服装等:汚れても良い服装、 事前に爪を切っておいて下さい。
収蔵資料展示 「生活と共に歩んできた鉄瓶」
湯を沸かし、茶碗に注ぐ道具として生活に欠かせない鉄瓶。当時の囲炉裏があった様子など想像しながらご覧下さい。
- 会期:12月6日(水)〜 12月27日(水)
- 場所:博物館本館受付前
- この展示の観覧料は無料です。
開館記念イベント「もちつき大会」
博物館が開館したのは昭和53 (1978)年12月28日、今年で45周年になります。開館を記念し、恒例の臼と杵による「もちつき大会」を開催します。今年の締めと来年への期待を込め、日本の伝統行事であるもちつきに参加しませんか?あんこやきな粉、みたらしなど、いろんなバリエーションで、 つきたての柔らかいおもちを味覚でも楽しんでください。
- 日時:12月24日(日) 10:00〜11:30(悪天候の場合は中止)
- 場所:博物館前庭
- 申込み:必要・定員60 名 (協力会会員 優先受付 )
- 申込先:知床博物館 (0152)23-1256
- 参加費:無料
- 服装:暖かい服装
- 協力:知床博物館協力会
11月
特別展 斜里平野の魅力〜人と自然による景観形成の歴史〜
四季折々の雄大な風景をわたしたちに魅せてくれる斜里平野がいかにして今日の景観へと変わっていったのか?そこには大きな気候変動と開拓者のたゆまぬ努力の歴史がありました。この特別展をご覧になることで 、きっと平野の魅力と歴 史を学ぶことができます。開催期間中にぜひご来館ください。
- 会期:9月23日(土)〜12月17日(日)
- 場所:交流記念館ホール
- ※ロビー展のみの観覧は無料です。
特別展講演会「アイヌ語地名から探る斜里平野・1万年の歴史」
特別展「斜里平野の魅力」に伴う特別講演会を開催します。
講演会:「アイヌ語地名から探る斜里平野 1万年の歴史」
この講演では、斜里に残る「シュマトゥカリ」という不思議なアイヌ語地名を手がかりとして、アイヌの人たち、そして人類はいつから斜里平野に住んでいたのか?という大きな問題にふれていきます。
マンモスを追ってきた旧石器人、気候の温暖化に適応して土器を発明した縄文人、オホーツク海からやってきたオホーツク文化人、さまざまな人類が混じり合い、変容し、交流した斜里平野は、日本列島のなかで、実はもっとも興味深い歴史を秘めた場所なのです!自然と人間がつくってきた1万年以上前の氷河期からたどる斜里平野の「景観(ランドスケープ)」の歴史をのぞいてみましょう。
- 日時:11月25日(土) 開演 13:30 〜15:00 頃
- 場所:博物館本館2階 映像展示室
- 料金:無 料(※要事前申込み/定員30名)
- 講 師:小野 有五さん 北海道大学名誉教授、1948年東京都生まれ。専門は地理学(理学博士)。「たたかう地理学」(2013年)で日本地理学会賞、日本人文地理学会賞を受賞。
- その他:講演会終了後に特別展のミニレクチャーを行います (希望者)。
- 申込先:知床博物館 (0152-23-1256)
収蔵資料展示 「根北線の定期券」
越川と斜里の間を結んだ国鉄根北線は、1970(昭和45)年に廃線になるまで、地域の大切な交通手段でした。学生たちが毎日のように使った小さな定期券から、当時の賑わいに思いを馳せてみてください。
- 会期:11月8日(水)〜 12月3日(日)
- 場所:博物館本館受付前
- ※この展示の観覧料は無料です。
博物館講座「秋の星座と木星・土星観察会」
秋の星座には、明るく輝く一等星はありませんがアンドロメダ大星雲やペルセウス座の二重星団など天体望遠鏡で見て楽しい天体が多くあります。また、木星と土星もまだ見頃です。ぜひご参加ください。
- 日時:11月10日(金)19:00〜20:00
- 集合場所:知床博物館交流記念館前
- 講師:合地 信生学芸員
- 参加費:無料
- 申込み:必要(定員6名)
- 申込先:知床博物館(0152)23ー1256
- 持ち物:暖かい服装
10月
第42回特別展 斜里平野の魅力〜人と自然による景観形成の歴史〜
斜里平野の人と自然の営みに注目した特別展を開催しています。明治時代の殖民区画をベースにして景観が作られてきた歴史を探ります。
- 会期:9月23日(土)〜12月17日(日)
- 場所:交流記念館ホール
- ※ロビー展のみの観覧は無料です。
高山植物園「草取りボランティア」
今年最後の草取りボランティアです。是非ご参加ください。
- 日時:10月13日(金) 9:00〜10:00(雨天中止)
- 場所:高山植物園(博物館裏のワシ小屋付近)
- 持ち物:帽子、軍手、虫除け
- 申し込み:不要(当日、直接現地にお越しください)
施設公開「農業資料等収蔵施設一般公開」
農業資料等収蔵施設(旧朱円小学校校舎 )を一般公開します。ワークショップも行います。あわせて、音楽などを聴きなが らゆっくりできる空間の提供と、手作りパンやお菓子、飲み物の販売を行う「のんびりバザール」も開催されますので、この機会にぜひご来館ください。
- 日時:10月25日(水) 9:30〜16:30
- 場所:斜里町農業資料等収蔵施設(旧朱円小学校)
- ※郷土史などの朗読会等も予定しています。
博物館講座「網走・常呂の地質観察会」
網走地域には知床半島より少し古い約1,000万年前の海底火山活動の地層が分布し、常呂地域にはさらに古い約6,000万年前の地層があります。これらから道東のでき方について考えてみます。
《おもな観察ポイント》
浜小清水海岸の鳴り砂、ポンモイの柱状節理、二ツ岩の水冷破砕岩、 能取岬の海食台地、常呂川で黒曜石探し、常呂変成帯の石灰岩
- 日時:10月21日(土)8:30〜16:30
- 集合・解散場所:知床博物館交流記念館前
- 講師:合地 信生学芸員
- 参加費:300円(協力会会員は無料)
- 定員:6名
- 申込み:必要
- 申込先:知床博物館(0152)23ー1256
- 持ち物:弁当、雨具、筆記道具
姉妹町盟約50周年記念「赤瓦三線ミニライブfrom竹富島」
姉妹町盟約50周年と交流記念館30周年を記念して、芸能の宝庫である竹富島で活躍している方々による三線ミニライブを開催します。竹富町の伝統的建物である赤瓦民家のもと、臨場感と島の情緒たっぷりに演奏します。南国の風を是非堪 能してください。
- 日 時:10 月 29 日(日)開 演:13:30
- 場所:交流記念館交流展示室
- 共催:知床博物館、姉妹町友好都市交流を進める会、竹富島三線ライブ実行委員会
- 料金:無料
- 申込:不要
収蔵資料展示 「澱粉工場の法被(はっぴ)」
町内では、かつて延べ200軒を超える澱粉工場が営まれていました。以久科で昭和40年代まで営まれていた山田澱粉工場の法被から、活気あふれる生産現場の雰囲気を想像してみてください。
- 会期:10月4日(水)〜 11月5日(日)
- 場所:博物館本館受付前
- ※この展示の観覧料は無料です。
9月
第42回特別展 斜里平野の魅力〜人と自然による景観形成の歴史〜
斜里平野の人と自然の営みに注目した特別展を開催します。明治時代の殖民区画をベースにして景観が作られてきた歴史を探ります。
- 会期:9月23日(土)〜12月17日(日)
- 場所:交流記念館ホール
- ※ロビー展のみの観覧は無料です。
ギャラリートーク 第42回特別展 斜里平野の魅力〜人と自然による景観の歴史〜
- 日時:①9月24日(日)10:00〜10:40 ②9月30日(土)11:00〜11:40(二回とも同じ内容です)
- 場所:交流記念館ホール
- 講師:村田 良介学芸員
- 申込:不要
- 講座「斜里平野の魅力地訪問」の同日セット参加がおススメです。
講座「斜里平野の魅力地訪問」第42回特別展 斜里平野の魅力〜人と自然による景観形成の歴史〜
- 日時:①9月24日(日)13:00〜16:00 ②9月30日(土)13:00〜16:00(別の場所に行きます)
- 集合場所:交流記念館ホール
- 講師:村田 良介学芸員
- 定員:各12名
- 申込:必要・先着順
- 申込先:知床博物館(0152)23-1256
- ギャラリートークの同日セット参加がおススメです。
高山植物園「草取りボランティア」
色とりどりの草花に季節を感じながら作業をしてみませんか?ご都合のつく時に是非ご参加ください。
- 日時:9月8日(金)9:00〜10:00(雨天中止)
- 場所:高山植物園(博物館裏のワシ小屋付近)
- 持ち物:帽子、軍手、虫除け
- 申し込み:不要(当日、直接現地にお越しください)
施設公開「農業資料等収蔵施設一般公開(秋期)」
農業資料等収蔵施設(旧朱円小学校)の秋の一般公開を行います。春の「音響機器」展示を引き続き開催し、蓄音機の実演奏や来館者がお持ちになるレコード鑑賞会なども行います。 音楽を聴きながらゆっくりできる空間の提供と、 手作りパンやお菓子、飲み物の販売を行う「のんびりバザール」も開催されますので、この機会にぜひご来館ください。
- 会期:9月20日(水) 〜24日(日)
- 時間:9:30〜16:30
- 場所:農業資料等収蔵施設(旧朱円小学校)
- 23日、24日の13:00頃に、蓄音機を使ったSPレコードの視聴を行います。
博物館講座「中秋の名月と土星・木星観察会」
大型天体望遠鏡でお月見をしましょう。隕石が衝突した月のクレーターや溶岩が流れた月の海を観察します。また、土星の環や木星の縞模様も見ます。盛りだくさんのメニューですので是非ご参加ください。
- 日時:9月29日(金)19:30〜20:30※悪天候の場合は30日(日)に延期
- 集合場所:知床博物館交流記念館前
- 講師:合地 信生学芸員
- 参加費:無料
- 申込み:必要
- 申込先:知床博物館(0152)23ー1256
収蔵資料展示 「アナログ時代の秤(はかり)」
これ、どっちが重い?郵便で送るならいくら? ちょっとした時に何かと必要な秤。デジタルが主流になった昨今では珍しく感じられるかもしれない、 アナログ式の秤を展示します
- 会期:9月6日(水)〜 10月1日(日)
- 場所:博物館本館受付前
- ※この展示の観覧料は無料です。
8月
ロビー展「はた織り作品展」
はたおりの会のみなさんが、ひとつひとつ丁寧に時間をかけて織った作品を展示します。新作も出品しますのでお楽しみに。
- 会期:8月5日(土)〜9月9日(土)
- 場所:交流記念館ホール
- ※ロビー展のみの観覧は無料です。
移動展示「音響機器展」
5月に朱円の農業資料等収蔵施設で開催された「音響機器展」を旧役場庁舎「葦の芸術原野祭」で一部移設します。
- 会期:8月4日(土)〜8月19日(土) 10:00〜17:00(月・火は休館)
- 場所:斜里町旧役場庁舎 ※本移動展は「葦の芸術原野祭」に併せ開催
- 入場料:無料
高山植物園「草取りボランティア」
色とりどりの草花に季節を感じながら作業をしてみませんか?ご都合のつく時に是非ご参加ください。今回は第2金曜日が祝日のため、8月10日(木)になりました。
- 日時:8月10日(木)9:00〜10:00(雨天中止)
- 場所:高山植物園(博物館裏のワシ小屋付近)
- 持ち物:帽子、軍手、虫除け
- 申し込み:不要(当日、直接現地にお越しください)
施設公開「農業資料等収蔵施設一般公開」
6月から旧朱円小学校で、月に1 回のペースで町民団体主催の「桜園のんびりバザール」が開催されています。これにあわせて、農業資料等収蔵施設も毎月一般公開します。9月は5日間連続での公開です。
- 会期:8月30日(水) 、9月20日(水)〜24日(日)
- 場所:農業資料等収蔵施設(旧朱円小学校)
博物館講座「夏の星座観察会」
こと座のベガ、白鳥座のデネブ、 ワシ座のアルタイルを結ぶ夏の大三 角形や天の川にある星雲・星団を天 体望遠鏡で観察します。
- 日時:8月5日(土)20:00〜21:00※悪天候の場合は8月6日(日)に延期
- 集合場所:知床博物館交流記念館前
- 講師:合地 信生学芸員
- 参加費:無料
- 申込み:必要
- 申込先:知床博物館(0152)23ー1256
収蔵資料展示 「樺太の白樺製カゴ」
私たちの住んでいる斜里町でも、 身近に見られる白樺とフレップ(苔桃)。樺太に住む少数民族の二ブフの人々がフレップを入れて運ぶために使った、白樺製のカゴを展示します。
- 会期:8月9日(水)〜 9月3日(日)
- 場所:博物館本館受付前
- ※この展示の観覧料は無料です。
7月
ロビー展 「ホネざんまい」
東京農業大学オホーツクキャンパス の学生が博物館実習の授業で製作した、骨の標本を展示します。 オオカミウオやトドの頭骨、エゾフクロウの全身骨格や羽毛などの力作のほ か、美味しいフライドチキンでつくった骨格標本の変わり種まで、ホネざんまいでお届けします。 普段は見ることのない様々な動物の骨から、その暮らしぶりを想像することも楽しいですが、あわせて近くの大学で行われている活動を身近に感じていただけたら幸いです。
- 会期:6月29日(木)〜7月16日(日)
- 場所:交流記念館ホール
- ※ロビー展のみの観覧は無料です。
収蔵資料展示 「昭和の虫かご」
蝶、クワガタ、キリギリスや バッタなど、昆虫採集というと子供の頃が思いだされます。昭和の竹ひごや金網と板で作られた虫かごを展示します。
- 会期:7月5日(水)〜8月6日(日)
- 場所:博物館本館受付前
- ※この展示のみの観覧は無料です。
高山植物園「草取りボランティア」
色とりどりの草花に季節を感じながら作業をしてみませんか?ご都合のつく時に是非ご参加ください。
- 日時:7月14日(金)9:00〜10:00(雨天中止)
- 場所:高山植物園(博物館裏のワシ小屋付近)
- 持ち物:帽子、軍手、虫除け
- 申し込み:不要(当日、直接現地にお越しください)
博物館講座「アンモナイト石鹸作り」
アンモナイトの型にグリセリンなどの薬品を注入し、アンモナイトの形の手作り石鹸を作ります。 お風呂場のメンバーに、アンモナイト石鹸をどうぞ。
- 日時:7月30日(日) 10:00〜11:30
- 場所:交流記念館実習室
- 定員:10名(要申し込み/小学4年生以上)
- 参加費:300円(小中学生、協力会員は無料)
- 講師:合地学芸員
- 申込先:斜里町立知床博物館 (0152)23-1256
6月
ロビー展 「ホネざんまい」
東京農業大学オホーツクキャンパスの学生が博物館実習の授業で製作した、骨の標本を展示します。 オオカミウオやトドの頭骨、エゾフクロウの全身骨格や羽毛などの力作のほか、美味しいフライドチキンでつくった骨格標本の変わり種まで、ホネざんまいでお届けします。 普段は見ることのない様々な動物の骨から、その暮らしぶりを想像することも楽しいですが、あわせて近くの大学で行われている活動を身近に感じていただけたら幸いです。
- 会期:6月29日(木)〜7月16日(日)
- 場所:交流記念館ホール
- ※ロビー展のみの観覧は無料です。
講座「知床の温泉観察会」
知床半島にはいろいろな泉質の温泉が湧出しています。岩尾別温泉や瀬石温泉(羅臼町)などを訪れ、温度計とペーハー計を使って、温泉の特徴を調べます。また、周りの地質との関係から泉質を推察します。羅臼の熊の湯に入浴予定。
- 日時:6月24日(土)9:00 〜16:00(小雨決行)
- 集合場所:博物館
- 講師:合地学芸員
- 定員:6名(高校生以上)※要申し込み
- 参加費:300円(協力会員無料)
- 持ち物:雨具、昼食、入浴用タオル、長靴、筆記用具
- 申込先:知床博物館(0152-23-1256)
講座「バスで行く・・チャシコツ岬上遺跡など町内遺跡巡り」
斜里町内には約400 か所の登録された遺跡がありますが、特に著名なオホーツク文化期のチャシコツ岬上遺跡(国指定)、縄文時代の朱円周堤墓群 (道指定)、同じく来運1遺跡(町指定) をバスで巡ります。
- 日 時 :6月18日 (日) 9:00 〜15:30※雨天実施
- 集合場所:博物館
- 訪問先:チャシコツ岬上遺跡、 朱円周堤墓群、来運1遺跡など (車中での解説あり)
- 講師:村田学芸員
- 定員:30 名 (要申し込み / 先着)
- 持ち物:保険代100円、昼食(自然センター)、軍手(チャシコツ岬上遺跡は急斜面を登ります)
- その他:自然センターで映像を見ます ( 希望者 600 円 )。
- チャシコツ岬上遺跡だけの参加者は 遺跡下に10時集合。チャシコツ岬上遺跡にはウルシが繁茂しているエリアがあります。
収蔵資料展示「お菓子をいれたガラス瓶」
昭和の頃、町内の商店街など、まち角のお店で使われた、昔懐かしいガラス瓶をご紹介します。彩り豊かな駄菓子が詰められていた様子を思い出して みてください。
- 会期:6月7日(水)〜7月2日(日)
- 場所:博物館本館受付前
- ※この展示の観覧料は無料です。
博物館みどりの日「花壇に花を植えにきませんか?」
知床博物館みどりの日では毎年、博物館駐車場脇の花壇に、たくさんの花を植え、来館者を迎えてきました。 今年度も下記の通り実施します。ご都合のよろしい方はぜひご参加ください。
- 日時:6月25日(日)10:00〜12:00
- 場所:知床博物館前庭
- 持ち物:帽子、軍手、虫除け
- 申し込み:不要(当日、直接現地にお越しください)
高山植物園「草取りボランティア」
今年もまた博物館裏にある高山植物 園の草取りボランティア活動が始まりますが、今年は日程を変更します。6月から10月まで 、毎月第2金曜 ( 祝日の場合は前日木曜 ) の9時から実施します。色とりどりの草花に季節を感じながら作業をしてみませんか?ご都合のつく時に是非ご参加ください。
- 日時:6月9日(金)9:00〜10:00(雨天中止)
- 場所:高山植物園(博物館裏のワシ小屋付近)
- 持ち物:帽子、軍手、虫除け
- 申し込み:不要(当日、直接現地にお越しください)
5月
ロビー展 北方民族博物館移動展
「暖かい」だけじゃない!毛皮と北方民族の多彩な関係
&ギャラリートーク
開催中のロビー展の関連イベントとして、北海道のアイヌやグリーンランドのイヌイットなど、寒い地域の先住民族の暮らしに詳しい専門家をお招きして、毛皮をめぐる物語と展示の魅力をじっくり語っていただくギャラリートークを開催します。
お申込みは不要です。たくさんの方のご参加をお待ちしております。
- 日時:5月6日(土)10:30〜12:00
- 場所:交流記念館応接室(集合)・交流記念館ホール
- 講師:日下 稜(北海道大学低温科学研究所)
□□□是澤 櫻子(国立アイヌ民族博物館)
□□□中田 篤(北方民族博物館) - 参加費:無料
施設公開
農業資料等収蔵施設の一般公開(春期)と「音響機器展」
農業資料等収蔵施設 ( 旧朱円小学校校舎 ) の春の一般公開を行います。昨年までの展示に加え、博物館から移転 し整理中の収蔵庫も公開し、普段は見られない資料を見ることできます。また、研修スペース(旧音楽室)では、「音響機器展」を開催し、音楽などを聴きながらゆっくりできる空間の提供や、出張ミュージアムショップもオープンしますので、この機会にぜひご来館ください。
- 会期:5月6日 (土)〜5月14日(日) ※5月8日(月)は休館です。
- 時間:9:30〜16:30
- 場所:斜里町農業資料等収蔵施設(旧朱円小学校)
- 6日(土)、7日(日)、13日(土)、14日(日13:00 頃に、蓄音機を使ったSPレコードの視聴を行います。
収蔵資料展示「明治・大正の美しい和食器」
四季折々の食材が盛り付けられ、生活に欠かせない存在だった和食器。明治から大正にかけて使われた、縁起が 良く美しい絵柄があしらわれた大皿や重箱を展示します。
- 会期:5月10日(水)〜6月4日(日)
- 場所:博物館本館受付前
- ※この展示の観覧料は無料です。
4月
ロビー展 北方民族博物館移動展
「暖かい」だけじゃない!毛皮と北方民族の多彩な関係
北方地域の諸民族は、衣類を始めとするさまざまな生活必需品の素材として動物の毛皮を活用してきました。また、美しい動物の毛皮は、他地域の交易品としても重要でした。本展示では、北方地域の代表的な動物とその毛皮を取り上げ、 それらがどのように活用されてきたのか、実物資料とともに紹介します。
- 会期:4月19日(水)〜 5月21日(日)
- 会場:交流記念館ホール
- ※この展示の観覧料は無料です。
博物館講座「春の星座観察会」
春の夜空の主役は、星座の中で 一番有名なおおくま座の北斗七星で す。北斗七星のひしゃくの柄から牛かい座、おとめ座につながる「春の大曲線」を探してみましょう。また、ヘルクレス座の球状星団も天体望遠鏡で観察します。西の空にはオリオン座などの冬の星座も見ることができます。
- 日時:4月28日(金)19:30〜20:30※悪天候の場合は29日(日)、30日(日)に延期
- 集合場所:知床博物館交流記念館前
- 講師:合地 信生学芸員
- 参加費:無料
- 申込み:必要
- 申込先:知床博物館(0152)23ー1256
収蔵資料展示 端午の節句「五月人形」
子どもの健康と成長を願う端午の節句。大正から昭和の武者人形、弓太刀や三宝揃などを展示します。
- 会期:4月5日(水)〜 5月7日(日)
- 場所:博物館本館受付前
- ※この展示の観覧料は無料です。
3月
ロビー展「蜃気楼・幻氷写真展〜蜃気楼ハンター星弘之の世界vol.2」
福島県のアマチュア写真家・星弘之さんによる幻氷の写真展を、昨年に引き続き開催します。今回は、流氷の上位蜃気楼「幻氷(げんぴょう)」だけでなく蜃気楼の写真や動画も加えパワーアップしています。蜃気楼は空気の温度差によって遠くの景色が不思議な形に見える現象です。約50年間蜃気楼の撮影を続けている星さんが捉えた決定的瞬間にご注目ください。あわせて、かつて知床博物館に勤務していた佐藤トモ子さんや町内在住の仲間の蜃気楼写真も展示します。
- 会期:3月16日(木)〜 4月6日(木)
- 会場:交流記念館ホール
- ※この展示の観覧料は無料です。
3年ぶりにカフェを開催します「蜃気楼・幻氷カフェ」
写真展に先駆けて、星さん・佐藤さんから蜃気楼と幻氷の魅力をたっぷり語っていただきます。全国各地の最新情報や、蜃気楼の謎の解明など、超レア蜃気楼映像を交えながら紹介します。
- 日時:3月15日(水)18:30〜20:00
- 場所:交流記念館 2F 応接室
- 講師:星弘之(蜃気楼ハンター)・佐藤トモ子(気象予報士、知床蜃気楼・幻氷研究会代表)
- 参加費:大人200円(協力会員無料)
- 定員:13名(要申し込み)
- 申込先:知床博物館(0152-23-1256)
- 特典:写真展の先行観覧可能。
収蔵資料展示「昭和の計算機」
電気や電池を使わず、機械的なカラクリのみで計算をする手廻し式タイガー計算器、歯車で数値を累計し計算する円筒状の小型手廻し式クルタ計算機など、懐かしい昭和の計算機を展示します。
- 日時:3月8日(日)〜 4月2日(日)
- 場所:博物館本館受付前
- ※この展示の観覧料は無料です。
2月
ロビー展「知床の水辺を知る3つの研究」
豊かな自然を有する知床では毎年、様々な調査研究が進められています。その成果の一部は国内外の学会や学術論文などでも紹介されてきました。このロビー展では、【知床の水辺】をフィールドとした3つの研究「カワガラスとサケの密接な関係」「サケ研究の今」「イワウベツ川の魚たち〜今とこれから〜」について収蔵展示を交えながら、展示の中でわかりやすく解説します。知床の自然をより深く知る機会としていただけると幸いです。
- 会期:2月7日(火)〜 3月7日(火)
- 会場:交流記念館ホール
- ※この展示の観覧料は無料です。
講座「歩くスキーで行く神の子池観察会」
伏流水の湧き出し口が青色に見える神の子池へ、道道の入り口から歩くスキーで行きます。森の中を観察しながらの片道1時間の散策ののち、帰りに緑の湯に入って疲れをいやします。
- 日時:2月26日(日)9:00 〜15:00(悪天候の場合は中止)
- 集合場所:博物館本館
- 場所:神の子池他
- 講師:合地学芸員、阿部主任
- 定員:6名※要申し込み
- 参加費:300円(中学生以下・協力会員無料)
- 持ち物:歩くスキー各自持参(B &G 海洋センターで借りれます)、昼食、手ぬぐい、お風呂代(450円、18歳以下140円)、暖かい服装
- 申込先:知床博物館(0152-23-1256)
講座「スノーシューで冬の森を散策しよう」
スノーシューを履いて歩けば、夏では見ることができない動物たちの痕跡や景色を見ることができます。知床の森を一緒に歩いてみませんか。
- 日時:2月12日(日)8:00 〜12:30(悪天候の場合は中止)
- 集合場所:博物館本館
- 場所:ウトロの森(1〜2km程度の散策)
- 講師:臼井学芸員、能勢 峰、能勢 理恵学芸員補
- 定員:5名(小学生以上)※要申し込み
- 参加費:無料(スノーシューはお貸しします)
- 持ち物:スキーウエアー等暖かい服装
- 申込先:知床博物館(0152-23-1256)
資料展示 桃の節句「昭和の雛人形」
1933(昭和8年)に購入された雛人形を展示します。約90年前の雛人形ですが、時代を経てもなお華やかで品のある姿のままで、子どもたちの健やかな成長を見守り続けています。
- 日時:2月5日(日)〜 3月5日(日)
- 場所:博物館本館受付前
- ※この展示の観覧料は無料です。
1月
講座「冬の星座観察会」
冬の星座は明るい星が多く、7つもの一等星が輝いています。また、オリオン座大星雲、プレアデス星団(すばる)、西の空にはアンドロメダ大星雲や木星など有名な星雲・星団も多く見られます。冬の天体を望遠鏡で観察してみましょう。
- 日時:令和5年1月13日(金)18:30〜19:30(悪天候の場合は14日(土)、15日(日)に順延)
- 場所:博物館前庭、天体ドーム室
- 講師:合地学芸員
- 定員:20名、要申込み
- 申込先:知床博物館(0152-23-1256)
- 参加費:無料
※小中学生は送迎をお願いします。上記時間のうち途中参加、退場は自由です。
収蔵資料展示 冬の履き物「雪下駄」
ゴム製の長靴が普及する以前の明治中期〜昭和初期にかけて、北海道では冬の履物として下駄、雪駄、爪甲、深靴などが使用されていました。今回は冬の履物の中から「雪下駄」を紹介します。雪下駄は女性が主に晴れ着の際に履いたものです。おしゃれで工夫の凝らされた冬の履物をぜひご覧ください。
- 会期:令和5年1月4日(水)〜31日(火)
- 場所:博物館本館受付前
- ※この展示の観覧料は無料です。
12月
講座「斜里の小麦でヒンメリをつくろう」
ヒンメリとは麦わらでつくられた北欧フィンランドの伝統的な装飾です。クリスマスの飾りとして用いられることも多いヒンメリ。今回は7月に斜里で収穫された小麦わらでヒンメリをつくります。ぜひご参加ください。
- 日時:12月10日(土)10:00〜12:00
- 場所:交流記念館実習室
- 定員:10名
- 参加費:無料
- 講師:臼井学芸員、加賀田学芸員補
- 申込先:知床博物館(0152-23-1256)
講座「トンボ玉づくり」
ガラス棒をバーナーで溶かし、鉄棒に巻き付けてトンボ玉を作ります。今回は大人の方を中心に、じっくり時間をかけてたくさんのトンボ玉を作り表面にきれいな模様も付けてみましょう。
- 日時:12月18日(日)9時、10時、11時から各1時間
- 場所:交流記念館実習室
- 定員:各時間4名
- 参加費:300円(協力会員、中学生以下無料)
- 参加者:小学生以上
- 講師:合地学芸員
- 申込先:知床博物館(0152-23-1256)
開館記念イベント「もちつき大会(持ち帰りのみ)」
開館記念のもちつき大会を3年ぶりに開催します。例年は記念日(12月28日)に行いますが、参加しやすいように12月25日(日)に実施します。新型コロナ対策のため、ついた餅はその場で食べず、持ち帰りとします。
- 日時:12月25日(日)10:00〜11:30(悪天候の場合は中止)
- 場所:博物館前庭
- 参加費:無料(要申込、協力会員優先受付)
- 定員:60名
- 服装:暖かい服装
- 協力:知床博物館協力会
- 申込先:知床博物館(0152-23-1256)
ロビー展示「写真展 斜里平野」
「景観ハンター」を自称する村田良介さんの写真展です。「天に続く道」をはじめとする斜里平野の絶景を写真で紹介します。今回のテーマは「ドローンに負けない写真を撮れるか‥」とのこと。斜里岳や海別岳からの写真を交えて畑や防風林がつくりだす斜里平野の魅力をご覧ください。
- 会期:12月10日(土)〜1月29日(日)
- 場所:交流記念館ホール
- ※この展示の観覧料は無料です。
収蔵資料展示「大正から昭和の防寒手袋」
大正時代のズックと木綿製、昭和の初め頃のわらで編まれたもの、犬の毛皮を中表にしたものなど、「てっかえし」とも呼ばれていた様々な防寒手袋を展示します。当時の冬の暮らしを想像しながらご覧ください。
- 会期:12月1日(木)〜12月25日(日)
- 場所:博物館本館受付前
- ※この展示の観覧料は無料です。
11月
講演会「研究から見えてきた知床のヒグマのくらし」
市街地への出没や、農作物被害…そんな話題の多いヒグマですが、森の中では木の実を食べ、木陰で眠り、静かにたくましく生きているのだそうです。今回は知床で調査研究を続けてきたお二人からヒグマの調査研究と、それによって見えてきた知床のヒグマの暮らしぶりについてお話ししていただきます。
- 日時 11月26日(土)13:30〜
- 場所 交流記念館ホール
- 講師 白根 ゆり ・ 神保 美渚 (独立行政法人 北海道立総合研究機構)
- 申し込み不要
収蔵資料展示「大正浪漫な山高帽子」
大正時代、西洋文化の影響を受けて新しい流行を取り入れた「モボ・モガ」(モダンボーイ・モダンガールの略)の服装が流行しました。モボのファッションアイテムのひとつである「山高帽子」は、斜里で撮影された当時の写真にも身につけている人がよくみられます。今回は当博物館に収蔵されている山高帽子を展示します。
- 会期 10月26日(水)〜11月27日(日)
- 場所 博物館本館受付前
- ※この展示の観覧は無料です。
講座「皆既月食観察とスマホ撮影」
月が東の空から登り始めると間もなく欠け始め、19時17分に皆既月食が始まります。約1時間30分もの長い間、赤胴色の皆既月食が観察されます。今回は要望の多かったスマホを使って天体望遠鏡で見える月の撮影を行いますので、お持ちの方はぜひスマホをご持参ください。
- 日時 11月8日(火)19:00〜20:30(悪天の場合は中止)
- 集合場所 博物館前
- 講師 合地 信生学芸員
- 服装 暖かい服装
- 申込先 知床博物館(0152−23−1256)
ロビー展「はた織りの会展示」
はた織り会のみなさんが、丁寧に時間をかけて織った作品を交流記念館で展示しています。新作も出品していますので、是非ご覧ください。
- 日時 〜11月19日(土)まで
- 場所 交流記念館ホール
- ※ロビー展の観覧は無料です。
10月
収蔵資料展示「昭和のアコーディオンと楽器」
レトロな装飾の昭和時代に使用されていたアコーディオンなどの楽器を展示します。奏でられる音色を想像しながら是非ご覧ください。
- 会期 9月28日(水)〜10月23日(日)
- 場所 博物館本館受付前
- ※この展示の観覧は無料です。
講座「メノウひろいとメノウみがき」
火山活動の熱水(温泉)が、岩石のすき間で冷やされるとメノウができます。この講座では実際に知床半島(真鯉)でメノウを拾い、博物館に帰ってからそれをきれいに磨きます。
- 日時 10月23日(日)9:00〜12:00
- 集合場所 博物館前集合(悪天候の場合は中止)
- 講師 合地 信生学芸員
要参加申し込み(定員5名)定員に達しました- 参加費:300円
- ※本講座は博物館キッズとの共催講座です。
ロビー展「はた織りの会展示」
はた織り会のみなさんが、丁寧に時間をかけて織った作品を交流記念館で展示しています。新作も出品していますので、是非ご覧ください。
- 日時 〜11月19日(土)まで
- 場所 交流記念館ホール
- ※ロビー展の観覧は無料です。
9月
「斜里村の興りと川端家文書」
葦の芸術原野祭にて開催していた知床博物館移動展「斜里村の興りと川端家文書」を、交流記念館ロビーにて展示します。
明治維新後の法整備に伴って、明治10年頃からこのシャリの地にも行政区や郵便局が設置されました。開拓使や三県一局制など国による様々な試みのなか、最初の斜里郡各村戸長となった川端又三郎氏に関する文書が博物館に寄贈されました。当時の様子とその事実が確認できる川端家文書などを紹介します。
- 会期 8月30日(火)〜9月18日(日)まで
- 場所 知床博物館交流記念館ロビー
収蔵展「昭和の嫁入り道具」
昭和時代に自治会で所有されていて、結婚式に貸し出されていた朱塗酒器(三三九度セット)や嫁入り道具などを展示します。
- 会期 9月1日(木)〜9月25日(日)まで
- 場所 博物館本館受付前
- ※この展示の観覧は無料です。
ロビー展「はた織りの会展示」
はた織りの会のみなさんが、ひとつひとつ丁寧に時間をかけて織った作品を展示します。新作も出展しますのでお楽しみに。
- 会期 9月23日(金)〜11月19日(土)まで
- 場所 知床博物館交流記念館ロビー
- ※この展示の観覧は無料です。
講座「秋の星座と土星観察会」
秋の夜空には明るい1等星がなく、少し寂しい感じがしますが、アンドロメダ大星雲やペルセウス座の二重星団が見られます。アンドロメダ大星雲は双眼鏡でも見ることができますので、探してみましょう。輪を持つ土星や縞模様の木星も天体望遠鏡で観察します。
- 日時 9月23日(金)20:00〜21:00(悪天の場合は9月24日(土)、25日(日)に延期)
- 場所 博物館前に集合
- 講師 合地 信生学芸員
- 要申し込み 知床博物館 23-1256
施設公開「農業資料等収蔵施設」
旧朱円小学校をリニューアルした農業資料等収蔵施設の一般公開を行います。職員室を中心にした展示スペースでは、開墾から畑を耕し、作物を育て、収穫するまでに使われた農機具などを展示しています。収蔵庫として利用している体育館など、普段は見ることのできないバックヤードを見に来てください。
- 日時:9月7日(水) 〜 9 月11日(日)9:00〜16:00
- 場 所::斜里町朱円 32 番地 ( 旧朱円小学校)
- ※観覧料は無料です。
施設公開イベント「斜里農業の変遷についての解説」
農業資料等収蔵施設の一般公開に併せて、博物館協力会会員であり以久科で農家をされていた近藤正純さんによる解説を行います。ぜひご参加ください。
- 日時:9月11日(日) ①10:00〜 ②13:00〜
- 場 所::斜里町朱円 32 番地 ( 旧朱円小学校)
- 参加費:無料
- 申し込み:不要(先着20名まで)
8月
移動展「斜里村の興りと川端家文書」
明治維新後の法整備に伴って、明治10年頃からこのシャリの地にも行政区や郵便局が設置されました。開拓使や三県一局制など国による様々な試みのなか、最初の斜里郡各村戸長となった川端又三郎氏に関する文書が博物館に寄贈されました。当時の様子とその事実が確認できる川端家文書などを紹介します。
- 会期 8月6日(土)〜8月27日(土)まで
- 場所 斜里町旧役場庁舎
- ※本移動展は「葦の芸術原野祭」に併せ開催いたします。入場料は無料です。
収蔵展「昭和の玩具と雑誌」
知床博物館に収蔵されている昭和の玩具と雑誌を展示します。童心を思い起こすレトロで懐かしい玩具や雑誌をぜひご覧ください。
- 会期 7月27日(水)〜8月28日(日)まで
- 場所 博物館本館受付前
- ※この展示の観覧は無料です。
講座「北海道の石でキーホルダーを作ろう」
黒曜石、ジャスパー、ヒスイを磨いてオリジナルのキーホルダーを作ってみましょう。
- 日時 8月27日(土)10:00〜12:00
- 場所 交流記念館実習室
- 講師 合地 信生学芸員
- 参加費 大人400円、中学生以下と協力会員は無料
- 定員 10名
- 要申し込み 知床博物館 23-1256
- 服装等 汚れてもよい服装。事前に爪を切っておいてください。
講座「夏の星座と土星観察会」
こと座のベガ、白鳥座のデネブ、ワシ座のアルタイルを結ぶ夏の大三角形や天の川にある星雲・星団を天体望遠鏡で観察します。また、輪を持つ土星も見てみましょう。
- 日時 8月2日(火)20:00〜21:00(悪天の場合は8月3日(水)に変更)
- 場所 博物館前に集合
- 講師 合地 信生学芸員
- 要申し込み 知床博物館 23-1256
早朝草取りボランティア
6〜10月に実施しているボランティア草取りを今年も行います。よろしければご参加ください。
- 日時 8月10日(水)6:00〜7:00(雨天中止)
- 場所 高山植物園(博物館裏のワシ小屋付近)
- 持ち物 帽子、軍手、虫除け
夏休み講座「磯場の生き物採集観察会」悪天候の為中止
チャシコツ崎でたも網を使って魚や貝などの磯の生き物を捕まえて観察します。
- 日時 8月2日(火)8:30〜12:00
- 場所 博物館前に集合 チャシコツ崎へ
- 対象 小学生3年生から中学3年生
- 定員 12人
- 服装・持ち物 長袖、長ズボン、帽子、長めの靴下、タオル、着替え、飲み物
- 要申し込み 知床博物館 23-1256
夏休み講座「斜里の魚をさばいて食べよう」
斜里周辺の海でさばいて魚をさばいて、焼いたり煮たりして食べます。
- 日時 8月3日(水)9:00〜12:00
- 集合 博物館 交流記念館ロビー
- 対象 小学生4年生から中学3年生
- 定員 10人
- 服装・持ち物 汚れてもよい服、軍手、飲み物
- 要申し込み 知床博物館 23-1256
夏休み講座「はたおり体験」
所要時間は一人30分くらいです。初めての人もゆっくり織ることができます。
- 日時 8月4日(木)9:30〜14:30のうち30分
- 場所 博物館 交流記念館ロビー
- 対象 小学生1年生から中学3年生
- 定員 20人
- 指導 はたおりの会
- 要申し込み 知床博物館 23-1256
夏休み講座「トンボ玉つくり体験」
炎でガラスを溶かし、トンボ玉(ガラス玉)を作ります。所要時間は一人30分です。
- 日時 8月5日(金)9:00〜12:00のうち30分
- 集合 博物館 交流記念館ロビー
- 対象 小学生3年生から中学3年生
- 定員 12人
- 要申し込み 知床博物館 23-1256
7月
ロビー展「学校の変遷」関連イベント ギャラリートーク&懐かしのミニコンサート
現在交流記念館ホールで開催しているロビー展「学校の変遷」の資料を見ながら学校の歴史を解説します。 また校歌のミニコンサート(ピアノ) を行います。
- 日時 7月9日(土)10:00〜11:30
- 場所 交流記念館ホール
- 講師 村田 良介学芸員、加賀田 直子(ピアノ)
- 定員 20名程度(要申し込み 知床博物館 23-1256)
観察会「斜里平野地質観察会」
屈斜路火山の火砕流と豊かな水 量の斜里川で作られた斜里平野。 中斜里の採石場、来運の湧水、さくらの滝、神の子池、摩周カルデラ、小清水原生花園の鳴き砂などを観察し、斜里平野の成り立ちについて考えてみましょう。
- 日時 7月23日(土)9:00〜16:00まで(悪天候の場合は7月24日(日)に延期)
- 集合場所 博物館前庭
- 講師 合地 信生(知床博物館学芸員)
- 持ち物 雨具、長靴、お弁当、筆記用具
- 参加人数 7名(要参加申込、高校生以上)
- 参加費 300円(協力会員無料)
収蔵展「しれとこ斜里ねぷた小物」
1983(昭和58)年7月、弘前市との友好都市盟約を記念して「弘前ねぷた」が初めて斜里で出陣しました。今回はしれとこ斜里ねぷたに関する小物を展示します。
- 会期 6月29日(水)〜7月24日(日)
- 場所 博物館本館受付前
- ※この展示の観覧は無料です。
早朝草取りボランティア
6月から10月まで、毎月10日に実施していきます。よろしければご参加ください。
- 日時 7月10日(日)6:00〜7:00(雨天中止)
- 場所 高山植物園(博物館裏のワシ小屋付近)
- 持ち物 帽子、軍手、虫除け
- 申し込みは不要(当日、現地にお越しください。)
6月
知床博物館ロビー展「学校の変遷」
斜里町の学校は明治25年(130年前)の斜里尋常小学校の設置が始まりです。昭和20年代には小学校15校、中学校11校がありましたが、現在は小学校2校、中学校1校、小中一貫の義務教育学校1校です。学校の変遷を産業や人口の変化と併せて紹介します。
- 会期 6月28日(火)〜8月21日(日)まで
- 場所 交流記念館ホール
- 主催 知床博物館
- ※この展示の観覧は無料です。
収蔵資料展示「昭和レトロなかき氷製造機」
本体に描かれた人工衛星や天体望遠鏡が当時の時代背景を感じさせます。
- 会期 5月25日(水)〜6月26日(日)
- 場所 博物館本館受付前
- ※本展示のみの観覧は無料です。
観察会「知床半島一周 地質観察会」
最近、羅臼側で地質観察会をする機会が多くなり、斜里川も含めた知床半島全体の火山活動の歴史が明らかになってきました。斜里川から羅臼側へと車で移動しながら、半島の両側で火山活動がどのように起こったのかを観察します。
- 日時 6月25日(土)8:30〜16:30まで
- 集合場所 博物館前庭
- 講師 合地 信生(知床博物館学芸員)
- 持ち物 雨具、長靴、お弁当、筆記用具
- 参加人数 7名(要参加申込、高校生以上)
- 参加費 300円(協力会員無料)
- ※この展示の観覧は無料です。
博物館みどりの日 花壇に花を植えにきませんか?
知床博物館みどりの日では毎年、博物館駐車場脇の花壇に、たくさんの花を植え、来館者を迎えてきました。今年度も下記の通り実施します。ご都合のよろしい方はぜひご参加ください。
- 日時 6月26日(日)10:00〜12:00
- 場所 博物館前庭
- 持ち物 帽子、軍手、虫除け
- 申し込みは不要(当日、現地にお越しください。)
高山植物園 草取りボランティアが始まります
今年も、博物館裏にある高山植物園の草取りボランティア活動が始まります。朝の涼しい時間に、色とりどりの草花を眺めながら作業をしてみませんか。6月から10月まで、毎月10日に実施していきます。ぜひご都合のつく日にご参加ください。
- 日時 6月10日(金)6:00〜7:00(雨天中止)
- 場所 高山植物園(博物館裏のワシ小屋付近)
- 持ち物 帽子、軍手、虫除け
- 申し込みは不要(当日、現地にお越しください。)
5月
ギャラリートーク
北海道立北方民族博物館の学芸員が移動展の展示解説に加え、ユーラシア大陸北部の遊牧文化についてお話します。
- 日時 5月14日(土)13:00〜14:00頃まで
- 場所 交流記念館ホール
- 講師 中田 篤(北方民族博物館学芸員)
- 参加人数 15名程度(要申し込み)
- 参加費 無料
観察会「斜里ーウトロ地質観察会」
博物館で作成し、YouTubeで配信したおうちでブラ合地「知床の石➀」の地質ポイントを現地でより詳しく観察します。今回の観察テーマはマグマの深い場所から浅い場所への移動です。また、チャシコツ崎(カメ岩)のでき方についても考えてみます。
- 日時 5月28日(土)8:30〜12:00頃まで 雨天時は 29日(日)に延期
- 場所 博物館前庭集合
- 講師 合地 信生学芸員
- 参加人数 7名(要申し込み)
- 持ち物 雨具、長靴、筆記用具
- 参加費 300円(中学生以下、協力会会員無料)
4月
北方民族博物館移動展「トナカイと暮らす̶タイガの遊牧民たち」
ユーラシア大陸北部で広く先住民の生業として営まれてきたトナカイ遊牧は、自然環境や携わる民族集団によって地域ごとに多様な展開をみせてきました。この展示では、シベリア東部から南部にかけてのタイガ地域に広がるトナカイ遊牧文化について紹介します。
- 会期 4月27日(水)~ 6月19日(日)まで
- 主催 北海道立北方民族博物館・知床博物館
- 場所 交流記念館ホール
収蔵資料展示「アンティークな手回し式ミシン」
足踏み式が主流になる前の、昭和初期に製造された手回しミシンを展示します。丸みのあるボデイ、ロゴのデザイン、模様など細部にこだわりがあり、アンティークな雰囲気を醸し出しています。
- 会期 3月19日(土)~5月22日(日)
- 場所 本館受付前
※この展示の観覧は無料です。
3月
おうちで楽しむブラ合地 第 1 弾!「知床の石・いろいろ!」
合地学芸員の地質観察会を、今回は配信によりおうちでお楽しみいただけます!知床半島は、峰浜付
近の半島基部の海岸線に堆積岩、それから先端部にかけての海岸線に海底火山活動の地層、そして半島の中軸部には陸上火山活動の岩石があります。第1弾として、1. 野外での露頭観察、2. 手にとっての観察、3. 顕微鏡での観察、4. そのでき方について、写真や図を用いて解説します。
- 配信日 3月25日(金)~5月末
- 配信方法 視聴希望者にYoutubeの期間限定URLをメールでお送りします。
- 申込方法 件名を「配信希望」とし、お名前、電話番号を明記の上、博物館へメール(shiretoko-m@sea.plala.or.jp) してください。難しい場合は博物館へ電話にてお申し込みください。
ロビー展「幻氷写真展~蜃気楼ハンター 星弘之の世界~」
40年来「蜃気楼ハンター」として蜃気楼の研究や撮影を続けているアマチュア写真家・星弘之さんによる幻氷の写真展を開催します。
斜里町を中心としたオホーツクエリアでは、流氷が海岸を離れていく春先、めずらしい流氷の上位蜃気楼「幻氷(げんぴょう)」が現れます。幻氷の魅力に取りつかれ、ほぼ毎春、星さんが斜里町に長期滞在して捉えた決定的瞬間を展示します。
会場のモニターでは、迫力ある動きの幻氷動画や、斜里近辺の仲間(知床蜃気楼・幻氷研究会)が撮影した写真もご紹介します。ぜひこの機会にお立ち寄りください。
- 会期 3月16日(水)~4月6日(水)
- 場所 交流記念館ホール
2月
流氷観察会
冬のオホーツク海の魅力のひとつに流氷があります。浜でとった流氷や”つらら”、洗面器で凍らせた氷の結晶をノコギリで切断したり、偏光板を使って観察したりして、その出来かたを考えます。海岸ではクリオネが見えるかもしれません!
- 日時 2月19日(土)10:00~11:30
- 場所 博物館実習室、前浜
- 講師 合地学芸員
- 服装 暖かい格好(帽子、手袋など)
- 定員 15名
今から90年前のひな人形
今から約90年前の1933(昭和8)年に購入されたひな人形を展示します。時代を経てもその華やかさを今に伝えています。今回は昭和の羽子板も合わせて展示します。ひな人形は、災厄を人形にのせて川に流す行事と人形遊びが結びついたものと考えられています。羽子板も邪気払いの意味があるとされ、健康を願う気持ちにつながるといえるでしょう。
- 会期 2月1日(火)~3月15日(火)
- 場所 本館受付前
1月
ロビー展 樺太(絵ハガキに見る樺太の記憶~知られざる北の国境)
日本が統治していた時代の樺太(サハリン)で販売されていた絵葉書を展示します。当時のサハリンの街並みや森林、動物といった自然の様子など、当時のさまざまな風景を伺い知ることができます。
- 期間: ~令和4年1月30日(日)
- 場所:交流記念館ホール
厳寒の天体観察会
冬の星座は明るい星が多く、7つもの1等星が輝いています。またオリオン座大星雲、プレアデス星団(すばる)、西の空にはアンドロメダ大星雲など有名な星雲・星団も多く見られます。冬の天体を望遠鏡で観察してみましょう。
- 日時:令和4年1月21日(金)18:30~19:30、
- 悪天候の場合は22、23日に順延
- 場所:博物館前庭、天体ドーム室
- 講師:村上館長、合地学芸員
- 定員:20名
- ※小中学生は送迎をお願いします。上記時間のうち途中加参加、退場は自由
博物館カフェ「アイヌ語地名から探る絶滅危惧種カワシンジュガイの棲む川!」
カワシンジュガイという川に棲む二枚貝を見たことがありますか?この貝は、綺麗な川にしか棲めな
いことから、棲む川を特定することで現在の川の環境を伺い知ることができます。北海道に残るアイヌ
語地名には、このカワシンジュガイとその仲間の貝を意味する地名が数多く残っています。では、北海
道のどこにどれくらい地名が残っているのでしょうか?地名の残る川には現在もこの貝が暮らすので
しょうか?今年度行った現地調査の様子や結果を、写真や映像を用いて、三浦学芸員がご紹介します!
- 日時:令和4年1月20日(木)18:30~19:30
- 場所:交流記念館2F会議室
- 定員:15名、要申込、参加無料
- ※中学生以上対象を想定しています。
化石レプリカづくり体験!(博物館キッズ拡大版)
大昔に生きていたアンモナイトの化石レプリカを石膏を使って作ってみます!
- 日時:令和4年1月16日(日)9:00~11:30
- 場所:交流記念館2F実習室
- 定員:5名、要申込、参加無料、小3以上対象
9月
「斜里村の興りと川端家文書」
葦の芸術原野祭にて開催していた知床博物館移動展「斜里村の興りと川端家文書」を、交流記念館ロビーにて展示します。
明治維新後の法整備に伴って、明治10年頃からこのシャリの地にも行政区や郵便局が設置されました。開拓使や三県一局制など国による様々な試みのなか、最初の斜里郡各村戸長となった川端又三郎氏に関する文書が博物館に寄贈されました。当時の様子とその事実が確認できる川端家文書などを紹介します。
- 会期 8月30日(火)〜9月18日(日)まで
- 場所 知床博物館交流記念館ロビー
収蔵展「昭和の嫁入り道具」
昭和時代に自治会で所有されていて、結婚式に貸し出されていた朱塗酒器(三三九度セット)や嫁入り道具などを展示します。
- 会期 9月1日(木)〜9月25日(日)まで
- 場所 博物館本館受付前
- ※この展示の観覧は無料です。
ロビー展「はた織りの会展示」
はた織りの会のみなさんが、ひとつひとつ丁寧に時間をかけて織った作品を展示します。新作も出展しますのでお楽しみに。
- 会期 9月23日(金)〜11月19日(土)まで
- 場所 知床博物館交流記念館ロビー
- ※この展示の観覧は無料です。
講座「秋の星座と土星観察会」
秋の夜空には明るい1等星がなく、少し寂しい感じがしますが、アンドロメダ大星雲やペルセウス座の二重星団が見られます。アンドロメダ大星雲は双眼鏡でも見ることができますので、探してみましょう。輪を持つ土星や縞模様の木星も天体望遠鏡で観察します。
- 日時 9月23日(金)20:00〜21:00(悪天の場合は9月24日(土)、25日(日)に延期)
- 場所 博物館前に集合
- 講師 合地 信生学芸員
- 要申し込み 知床博物館 23-1256
施設公開「農業資料等収蔵施設」
旧朱円小学校をリニューアルした農業資料等収蔵施設の一般公開を行います。職員室を中心にした展示スペースでは、開墾から畑を耕し、作物を育て、収穫するまでに使われた農機具などを展示しています。収蔵庫として利用している体育館など、普段は見ることのできないバックヤードを見に来てください。
- 日時:9月7日(水) 〜 9 月11日(日)9:00〜16:00
- 場 所::斜里町朱円 32 番地 ( 旧朱円小学校)
- ※観覧料は無料です。
施設公開イベント「斜里農業の変遷についての解説」
農業資料等収蔵施設の一般公開に併せて、博物館協力会会員であり以久科で農家をされていた近藤正純さんによる解説を行います。ぜひご参加ください。
- 日時:9月11日(日) ①10:00〜 ②13:00〜
- 場 所::斜里町朱円 32 番地 ( 旧朱円小学校)
- 参加費:無料
- 申し込み:不要(先着20名まで)
8月
移動展「斜里村の興りと川端家文書」
明治維新後の法整備に伴って、明治10年頃からこのシャリの地にも行政区や郵便局が設置されました。開拓使や三県一局制など国による様々な試みのなか、最初の斜里郡各村戸長となった川端又三郎氏に関する文書が博物館に寄贈されました。当時の様子とその事実が確認できる川端家文書などを紹介します。
- 会期 8月6日(土)〜8月27日(土)まで
- 場所 斜里町旧役場庁舎
- ※本移動展は「葦の芸術原野祭」に併せ開催いたします。入場料は無料です。
収蔵展「昭和の玩具と雑誌」
知床博物館に収蔵されている昭和の玩具と雑誌を展示します。童心を思い起こすレトロで懐かしい玩具や雑誌をぜひご覧ください。
- 会期 7月27日(水)〜8月28日(日)まで
- 場所 博物館本館受付前
- ※この展示の観覧は無料です。
講座「北海道の石でキーホルダーを作ろう」
黒曜石、ジャスパー、ヒスイを磨いてオリジナルのキーホルダーを作ってみましょう。
- 日時 8月27日(土)10:00〜12:00
- 場所 交流記念館実習室
- 講師 合地 信生学芸員
- 参加費 大人400円、中学生以下と協力会員は無料
- 定員 10名
- 要申し込み 知床博物館 23-1256
- 服装等 汚れてもよい服装。事前に爪を切っておいてください。
講座「夏の星座と土星観察会」
こと座のベガ、白鳥座のデネブ、ワシ座のアルタイルを結ぶ夏の大三角形や天の川にある星雲・星団を天体望遠鏡で観察します。また、輪を持つ土星も見てみましょう。
- 日時 8月2日(火)20:00〜21:00(悪天の場合は8月3日(水)に変更)
- 場所 博物館前に集合
- 講師 合地 信生学芸員
- 要申し込み 知床博物館 23-1256
早朝草取りボランティア
6〜10月に実施しているボランティア草取りを今年も行います。よろしければご参加ください。
- 日時 8月10日(水)6:00〜7:00(雨天中止)
- 場所 高山植物園(博物館裏のワシ小屋付近)
- 持ち物 帽子、軍手、虫除け
夏休み講座「磯場の生き物採集観察会」悪天候の為中止
チャシコツ崎でたも網を使って魚や貝などの磯の生き物を捕まえて観察します。
- 日時 8月2日(火)8:30〜12:00
- 場所 博物館前に集合 チャシコツ崎へ
- 対象 小学生3年生から中学3年生
- 定員 12人
- 服装・持ち物 長袖、長ズボン、帽子、長めの靴下、タオル、着替え、飲み物
- 要申し込み 知床博物館 23-1256
夏休み講座「斜里の魚をさばいて食べよう」
斜里周辺の海でさばいて魚をさばいて、焼いたり煮たりして食べます。
- 日時 8月3日(水)9:00〜12:00
- 集合 博物館 交流記念館ロビー
- 対象 小学生4年生から中学3年生
- 定員 10人
- 服装・持ち物 汚れてもよい服、軍手、飲み物
- 要申し込み 知床博物館 23-1256
夏休み講座「はたおり体験」
所要時間は一人30分くらいです。初めての人もゆっくり織ることができます。
- 日時 8月4日(木)9:30〜14:30のうち30分
- 場所 博物館 交流記念館ロビー
- 対象 小学生1年生から中学3年生
- 定員 20人
- 指導 はたおりの会
- 要申し込み 知床博物館 23-1256
夏休み講座「トンボ玉つくり体験」
炎でガラスを溶かし、トンボ玉(ガラス玉)を作ります。所要時間は一人30分です。
- 日時 8月5日(金)9:00〜12:00のうち30分
- 集合 博物館 交流記念館ロビー
- 対象 小学生3年生から中学3年生
- 定員 12人
- 要申し込み 知床博物館 23-1256
7月
ロビー展「学校の変遷」関連イベント ギャラリートーク&懐かしのミニコンサート
現在交流記念館ホールで開催しているロビー展「学校の変遷」の資料を見ながら学校の歴史を解説します。 また校歌のミニコンサート(ピアノ) を行います。
- 日時 7月9日(土)10:00〜11:30
- 場所 交流記念館ホール
- 講師 村田 良介学芸員、加賀田 直子(ピアノ)
- 定員 20名程度(要申し込み 知床博物館 23-1256)
観察会「斜里平野地質観察会」
屈斜路火山の火砕流と豊かな水 量の斜里川で作られた斜里平野。 中斜里の採石場、来運の湧水、さくらの滝、神の子池、摩周カルデラ、小清水原生花園の鳴き砂などを観察し、斜里平野の成り立ちについて考えてみましょう。
- 日時 7月23日(土)9:00〜16:00まで(悪天候の場合は7月24日(日)に延期)
- 集合場所 博物館前庭
- 講師 合地 信生(知床博物館学芸員)
- 持ち物 雨具、長靴、お弁当、筆記用具
- 参加人数 7名(要参加申込、高校生以上)
- 参加費 300円(協力会員無料)
収蔵展「しれとこ斜里ねぷた小物」
1983(昭和58)年7月、弘前市との友好都市盟約を記念して「弘前ねぷた」が初めて斜里で出陣しました。今回はしれとこ斜里ねぷたに関する小物を展示します。
- 会期 6月29日(水)〜7月24日(日)
- 場所 博物館本館受付前
- ※この展示の観覧は無料です。
早朝草取りボランティア
6月から10月まで、毎月10日に実施していきます。よろしければご参加ください。
- 日時 7月10日(日)6:00〜7:00(雨天中止)
- 場所 高山植物園(博物館裏のワシ小屋付近)
- 持ち物 帽子、軍手、虫除け
- 申し込みは不要(当日、現地にお越しください。)
6月
知床博物館ロビー展「学校の変遷」
斜里町の学校は明治25年(130年前)の斜里尋常小学校の設置が始まりです。昭和20年代には小学校15校、中学校11校がありましたが、現在は小学校2校、中学校1校、小中一貫の義務教育学校1校です。学校の変遷を産業や人口の変化と併せて紹介します。
- 会期 6月28日(火)〜8月21日(日)まで
- 場所 交流記念館ホール
- 主催 知床博物館
- ※この展示の観覧は無料です。
収蔵資料展示「昭和レトロなかき氷製造機」
本体に描かれた人工衛星や天体望遠鏡が当時の時代背景を感じさせます。
- 会期 5月25日(水)〜6月26日(日)
- 場所 博物館本館受付前
- ※本展示のみの観覧は無料です。
観察会「知床半島一周 地質観察会」
最近、羅臼側で地質観察会をする機会が多くなり、斜里川も含めた知床半島全体の火山活動の歴史が明らかになってきました。斜里川から羅臼側へと車で移動しながら、半島の両側で火山活動がどのように起こったのかを観察します。
- 日時 6月25日(土)8:30〜16:30まで
- 集合場所 博物館前庭
- 講師 合地 信生(知床博物館学芸員)
- 持ち物 雨具、長靴、お弁当、筆記用具
- 参加人数 7名(要参加申込、高校生以上)
- 参加費 300円(協力会員無料)
- ※この展示の観覧は無料です。
博物館みどりの日 花壇に花を植えにきませんか?
知床博物館みどりの日では毎年、博物館駐車場脇の花壇に、たくさんの花を植え、来館者を迎えてきました。今年度も下記の通り実施します。ご都合のよろしい方はぜひご参加ください。
- 日時 6月26日(日)10:00〜12:00
- 場所 博物館前庭
- 持ち物 帽子、軍手、虫除け
- 申し込みは不要(当日、現地にお越しください。)
高山植物園 草取りボランティアが始まります
今年も、博物館裏にある高山植物園の草取りボランティア活動が始まります。朝の涼しい時間に、色とりどりの草花を眺めながら作業をしてみませんか。6月から10月まで、毎月10日に実施していきます。ぜひご都合のつく日にご参加ください。
- 日時 6月10日(金)6:00〜7:00(雨天中止)
- 場所 高山植物園(博物館裏のワシ小屋付近)
- 持ち物 帽子、軍手、虫除け
- 申し込みは不要(当日、現地にお越しください。)
5月
ギャラリートーク
北海道立北方民族博物館の学芸員が移動展の展示解説に加え、ユーラシア大陸北部の遊牧文化についてお話します。
- 日時 5月14日(土)13:00〜14:00頃まで
- 場所 交流記念館ホール
- 講師 中田 篤(北方民族博物館学芸員)
- 参加人数 15名程度(要申し込み)
- 参加費 無料
観察会「斜里ーウトロ地質観察会」
博物館で作成し、YouTubeで配信したおうちでブラ合地「知床の石➀」の地質ポイントを現地でより詳しく観察します。今回の観察テーマはマグマの深い場所から浅い場所への移動です。また、チャシコツ崎(カメ岩)のでき方についても考えてみます。
- 日時 5月28日(土)8:30〜12:00頃まで 雨天時は 29日(日)に延期
- 場所 博物館前庭集合
- 講師 合地 信生学芸員
- 参加人数 7名(要申し込み)
- 持ち物 雨具、長靴、筆記用具
- 参加費 300円(中学生以下、協力会会員無料)
4月
北方民族博物館移動展「トナカイと暮らす̶タイガの遊牧民たち」
ユーラシア大陸北部で広く先住民の生業として営まれてきたトナカイ遊牧は、自然環境や携わる民族集団によって地域ごとに多様な展開をみせてきました。この展示では、シベリア東部から南部にかけてのタイガ地域に広がるトナカイ遊牧文化について紹介します。
- 会期 4月27日(水)~ 6月19日(日)まで
- 主催 北海道立北方民族博物館・知床博物館
- 場所 交流記念館ホール
収蔵資料展示「アンティークな手回し式ミシン」
足踏み式が主流になる前の、昭和初期に製造された手回しミシンを展示します。丸みのあるボデイ、ロゴのデザイン、模様など細部にこだわりがあり、アンティークな雰囲気を醸し出しています。
- 会期 3月19日(土)~5月22日(日)
- 場所 本館受付前
※この展示の観覧は無料です。
3月
おうちで楽しむブラ合地 第 1 弾!「知床の石・いろいろ!」
合地学芸員の地質観察会を、今回は配信によりおうちでお楽しみいただけます!知床半島は、峰浜付
近の半島基部の海岸線に堆積岩、それから先端部にかけての海岸線に海底火山活動の地層、そして半島の中軸部には陸上火山活動の岩石があります。第1弾として、1. 野外での露頭観察、2. 手にとっての観察、3. 顕微鏡での観察、4. そのでき方について、写真や図を用いて解説します。
- 配信日 3月25日(金)~5月末
- 配信方法 視聴希望者にYoutubeの期間限定URLをメールでお送りします。
- 申込方法 件名を「配信希望」とし、お名前、電話番号を明記の上、博物館へメール(shiretoko-m@sea.plala.or.jp) してください。難しい場合は博物館へ電話にてお申し込みください。
ロビー展「幻氷写真展~蜃気楼ハンター 星弘之の世界~」
40年来「蜃気楼ハンター」として蜃気楼の研究や撮影を続けているアマチュア写真家・星弘之さんによる幻氷の写真展を開催します。
斜里町を中心としたオホーツクエリアでは、流氷が海岸を離れていく春先、めずらしい流氷の上位蜃気楼「幻氷(げんぴょう)」が現れます。幻氷の魅力に取りつかれ、ほぼ毎春、星さんが斜里町に長期滞在して捉えた決定的瞬間を展示します。
会場のモニターでは、迫力ある動きの幻氷動画や、斜里近辺の仲間(知床蜃気楼・幻氷研究会)が撮影した写真もご紹介します。ぜひこの機会にお立ち寄りください。
- 会期 3月16日(水)~4月6日(水)
- 場所 交流記念館ホール
2月
流氷観察会
冬のオホーツク海の魅力のひとつに流氷があります。浜でとった流氷や”つらら”、洗面器で凍らせた氷の結晶をノコギリで切断したり、偏光板を使って観察したりして、その出来かたを考えます。海岸ではクリオネが見えるかもしれません!
- 日時 2月19日(土)10:00~11:30
- 場所 博物館実習室、前浜
- 講師 合地学芸員
- 服装 暖かい格好(帽子、手袋など)
- 定員 15名
今から90年前のひな人形
今から約90年前の1933(昭和8)年に購入されたひな人形を展示します。時代を経てもその華やかさを今に伝えています。今回は昭和の羽子板も合わせて展示します。ひな人形は、災厄を人形にのせて川に流す行事と人形遊びが結びついたものと考えられています。羽子板も邪気払いの意味があるとされ、健康を願う気持ちにつながるといえるでしょう。
- 会期 2月1日(火)~3月15日(火)
- 場所 本館受付前
1月
ロビー展 樺太(絵ハガキに見る樺太の記憶~知られざる北の国境)
日本が統治していた時代の樺太(サハリン)で販売されていた絵葉書を展示します。当時のサハリンの街並みや森林、動物といった自然の様子など、当時のさまざまな風景を伺い知ることができます。
- 期間: ~令和4年1月30日(日)
- 場所:交流記念館ホール
厳寒の天体観察会
冬の星座は明るい星が多く、7つもの1等星が輝いています。またオリオン座大星雲、プレアデス星団(すばる)、西の空にはアンドロメダ大星雲など有名な星雲・星団も多く見られます。冬の天体を望遠鏡で観察してみましょう。
- 日時:令和4年1月21日(金)18:30~19:30、
- 悪天候の場合は22、23日に順延
- 場所:博物館前庭、天体ドーム室
- 講師:村上館長、合地学芸員
- 定員:20名
- ※小中学生は送迎をお願いします。上記時間のうち途中加参加、退場は自由
博物館カフェ「アイヌ語地名から探る絶滅危惧種カワシンジュガイの棲む川!」
カワシンジュガイという川に棲む二枚貝を見たことがありますか?この貝は、綺麗な川にしか棲めな
いことから、棲む川を特定することで現在の川の環境を伺い知ることができます。北海道に残るアイヌ
語地名には、このカワシンジュガイとその仲間の貝を意味する地名が数多く残っています。では、北海
道のどこにどれくらい地名が残っているのでしょうか?地名の残る川には現在もこの貝が暮らすので
しょうか?今年度行った現地調査の様子や結果を、写真や映像を用いて、三浦学芸員がご紹介します!
- 日時:令和4年1月20日(木)18:30~19:30
- 場所:交流記念館2F会議室
- 定員:15名、要申込、参加無料
- ※中学生以上対象を想定しています。
化石レプリカづくり体験!(博物館キッズ拡大版)
大昔に生きていたアンモナイトの化石レプリカを石膏を使って作ってみます!
- 日時:令和4年1月16日(日)9:00~11:30
- 場所:交流記念館2F実習室
- 定員:5名、要申込、参加無料、小3以上対象